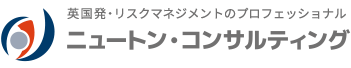-事業内容を教えてください。
当事務所は、2003年の社会保険労務士法の改正により、個人事務所である金田労務管理事務所から「社会保険労務士法人東京労務」に組織変更しました。企業の労働保険事務手続、社会保険事務手続、給与計算、労務相談等の業務をサポートしております。
職員数31名のうち、社会保険労務士15名を擁する当事務所は、業界内では大手の部類に入ります。相談業務については社労士事務所の規模に関係なく対応できますが、特に大規模企業の、とりわけ労働保険事務・社会保険事務等の実務代行までを行うにはある程度の規模が必要になります。当事務所は、人事・労務の専門家集団として顧問先企業に万全のサポート体制を提供しております。
-今回BCP策定に取り組まれた理由を教えてください。
東日本大震災の後、被災地を訪問し、自らが被災者であるにもかかわらず、地域住民の対応にあたっていた社会保険労務士たちを目の当たりにしました。社会保険労務士業の内訳として、社会保険業務、労働保険業務、労務相談、人事デューデリジェンス、個別労働紛争解決、給与計算業務等がありますが、これらの業務は広域災害発生時も継続性が求められます。
これらを踏まえて、当事務所も危機管理、事前の準備が必要であると認識し、BCPを策定することにしました。職員の安全を確保したうえで、事業を早期復旧・継続し、顧客からの信頼を得たいと思っております。
-策定されたBCPの内容を教えてください。
当事務所は、社労士の専門家集団であることから、BCPの対象は社会保険労務士業としました。災害時には新規の顧問契約の受付は行わず、既存顧客の社会保険労務士業務を継続することを優先します。但し、発災後の保険料の減免、納期限の延長、労災保険給付請求提出時の弾力的取扱い等の震災特例対応は社会的ニーズの観点から新規依頼を受け付けます。
これらを継続するには、社会保険労務士、事務職員、そして顧客情報が重要経営資源になりますが、発災後、職員の半数が出社・帰宅困難、事務所内は什器・備品が散乱、基幹業務用のサーバも破損すると想定しました。
通常は、職員ごとに担当顧客、担当業務が割り当てられていますが、発災後は、限られた人的資源での業務継続が必要となります。そのため、平時より業務の標準化、グループ体制での運用を行うこととし、属人性を低減、代替要員による業務代行を目指しました。顧客情報は、システムで維持・管理しており、セキュリティレベルの高い外部ストレージにバックアップを取るなどの対策を講ずることにしました。
| 対象事業 | 社会保険労務士業 |
|---|---|
| 対象リスク | 東京湾北部地震 |
| 被災シナリオ | 職員半数出社・帰宅困難(うち社会保険労務士6名) 事務所内什器・備品散乱 基幹業務(社労士業務)用サーバ破損 |
| 予防・低減策 | サーバ・什器・備品類の防震・転倒対策 印鑑等、重要資産の貸金庫への保管 |
| 代替策 | グループ体制によりバックアップ要員を育成し、代替要員にて業務代行 予備サーバへ切替、バックアップデータをリストア |
-苦労されたポイントや、新たな気付きはありましたか?
短期間で多くの事を検討し、多くの成果物を作らなければならないのはとても大変でした。反面、短期集中で作業に取り組んだからこそ、内容の濃い作業で初版のBCPを作成することができたと思います。以前、社内でBCP研修会を実施したことがありますが、進め方がまったくわかりませんでした。今回のように東京都BCP策定支援事業の力を借りて、後押ししてもらうことは当社にとって大きな価値がありました。
今回の作業を通じて、事業を継続するための視点に気付きました。重要な業務プロセスそのものに着目するのではなく、そこで使用する重要な経営資源に着目し、それを守る、あるいは失った場合の代替策を考えるという視点は新たな気付きでした。
-BCPを策定した感想をお願いします。
作業の過程で、プロジェクトメンバー内で、率直な意見、感想を出し合いながら取り組めたことは非常に良かったと思います。今回の活動結果を受けて、新たにBCPチームとITチームを編成し、BCPを推進していくことにしました。プライバシー・マーク・チームも併せてPDCAのサイクルを回し、BCPをさらにブラッシュ・アップしていきます。弊社は、人が財産なので、今後、インフルエンザ対応のBCPにも取り組んでいきたいと思います。
今回の活動を外部に向けて積極的にアピールし、顧客の皆さんに安心感を持っていただけるよう、努力してまいります。