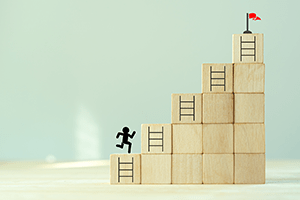
先日、面白い本を見つけました。「興味のある人はぜひ読んでみてください」で済む話ですが、なぜか日本語版が出版されていないようなので、この場を借りて、私の体験談を交えながら紹介をしたいと思います。
この本に手を出したのは、次のような一文に興味を惹かれたからです。
調査によると、新年の抱負の92%は失敗に終わります。毎年1月になると、人々は希望と熱意を持ってスタートし、今年こそが本当に新しい自分になる年だと信じています。しかし、スタートする人は100%でも、最後までやり遂げるのはわずか8%です。統計的には、あなたが目標を達成する確率は、ジュリアード音楽院に入学してバレリーナになる確率と同じです。その合格率は約8%です、ダンサーは狭き門です。(本書より)
本書は「決めたことを、どうすれば途中で挫折せずに、最後までやり切ることができるのか?」について徹底的に掘り下げた本です。以下が当てはまる人たちは本書の内容を知る価値があると言えるでしょう。
「年初に立てた計画を完遂しないことが多いな」
「上司と個人目標を設定するのだけど達成できた試しがないな」
「うちの組織では何かというと、やり始めたことは自然消滅しているな」
こうした読者の悩みに対して、誰にとってもシンプルかつ実践可能な解決策を提示してくれています。解決策は、本書の哲学とも言える礎の上に築かれています。それは「いかにして完璧主義を排除するか」というものです。
実際、大学の研究者がいくつか実験を行っており、その中には、目標達成率を最も引き上げることができたアプローチの1つが、ゴール達成のプレッシャーを取り除き、完璧主義を取り除くものだったそうです。著者は明言しています。「完璧を目指さない人ほど、生産性が高い」と。
この本の事例をそのまま載せるわけにはいかないので、それらに極めて近い私の体験談をご紹介します。ちなみに私は昔、完璧主義でした。
社会人になりたての頃、毎週ジムに通って筋トレをしていました。週2~3回くらいのノルマを自らに課していました。大変でしたがそれでも10ヶ月くらいは続いたんじゃないでしょうか。ある日、海外旅行をすることになり、ジムを休むことになりました。日本に戻ってきたので、そのままジムも再開すればよかったのですが、なぜかやる気が起きませんでした。次の週は、体の重さに比例するかのように「行かねば...いや、でも翌週から始めればいいかな...」と言う感じで、気持ちも重くなっていきました。長期間ジムを休んだ罪悪感と、そんなに休んでしまっては元の状態に戻るのには大変な労力がいるというやるせなさから、ジム通いが一気に消滅していきました。思えば、人生、そんなことの繰り返しだったように思います。ジョギングもやっていた時期がありましたが、似たような理由で消滅していきました。
またある時はこんなこともありました。アメリカ出張をした時のことです。そこでかなりストイックな米国人のビジネスマンにお会いしたのです。その方は「俺は健康のために毎日走っているよ」とおっしゃいました。私は聞きました。「長続きするコツはなんですか?」と。「コツは、雨だろうが、雪だろうが出張をしようが、走ると決めたら自分に言い訳をせず走ることだよ」と。「ああ、なるほど!自分は何かあるとそれを言い訳にしてバタンとやめてしまう癖がある。そしてそれが途中で辞める引き金になってしまうんだな。だったら、この人の言うとおり言い訳をする機会をなくせばいいんだ」と心に誓いました。
そこからは雨の日も雪の日も狂ったように走り続けました。米国出張の時も、知らない土地を夕方5時に走り、真冬のロシア出張が入った時ですら、大雪が降っていたのですが、それを言い訳にしちゃいけないと自分に言い聞かせ、全く見知らぬ土地を、早朝5時の薄暗い中で走りました。今思えば色々な意味で危険なことをやっていたと反省していますが、このやり方でそれなりに成果は出たんです。少なくとも数年間は継続することができたわけですから。
ですが、過ぎたるは及ばざるが如し。ある時、酷く体調を崩しました。バカな話ですが、体調を崩していたのに無理して走ったんです。その時は気合いで走れば風邪も早々に治ると心のどこかで思ってもいたのでしょう。すると、余計に体調を崩し、とてつもなく寝込む羽目になりました。今思えば、走るのは楽しくなかったですし、無理をしていたんでしょう。そうしたことをきっかけに走ることも終焉を迎えてしまいました。
その後、歳を重ねたこともあり、完璧主義に対する意識がだいぶ弱まってきました。「どれだけ努力しても完璧にやるのはそもそも無理」と言うことを学ぶ機会をたくさんもらうことができたおかげでもあります。物事に優先順位はつけなきゃいけないし、完璧にしないで7割くらいで全部を終わらせる方が、目的・目標達成には正しい場合があると言うことを身をもって体験していきました。
そんなこんなで今から3~4年前に改めて筋トレを再開する機会がありました。かなり緩い目標を設けました。しかもジムに行くのは「その行為自体」が億劫になることがあるので、家で気軽にできるようにすればいいやと思い、「週1回自宅で筋トレをする。その内容はなんでもあり」という目標を設定しました。功を奏したのが「筋トレは毎日やらなくても大丈夫。筋肉を維持するだけであれば週1回でも大丈夫。2回やれば筋肉が徐々にでもつき始める。仮に数週間やらなかったとしても、筋肉は記憶を覚えていて、トレーニングをすれば全くしてない人に比べて遥かに速いスピードで元の状態に戻る」という話を聞いたことです。そう聞いて心が楽になった気がしました。
そう言うマインドセットになったおかげで、継続が全く苦じゃなくなりました。辛いと思ったことはないし、辛いなと思ったら、1~2週間でも気軽にサボるようにしています。旅行が入ったり、体調が悪かったりで1ヶ月近く体を動かせないことがありましたが、その翌週は普通にトレーニングを再開していました。逆に体調のいい週は、2~3回トレーニングをすることも増えてきました。そんなこんなで今でも続いています。ゆるくやっていますが、筋肉はついてきています。最初は50回でも辛かった腹筋も今では3倍以上できるようになりました。「継続は力なり」です。
さて、本書から少し脱線してしまいましたが、本書には、まさにこうした点がコツの1つとして書かれています。例えば、目標の高さを、その半分にすると目標達成率が劇的に向上するというアプローチも実際に紹介しています。
研究者から送られてきた30日間のハッスル(実験)に関するレポートの中で、特に目を引く結果がありました。それは、目標を半分にした人たちが、過去の同様の目標関連のチャレンジと比較して、パフォーマンスが平均で63%向上したということです。(本書より)
「そりゃぁ、目標をゆるくした方が達成率が上がるのは当然じゃん」って思うかもしれませんが、ポイントはそこではないんです。目標をゆるくした方が、達成できる総量が多くなるということです。ですから本書は終始一貫して、いかに完璧主義という気持ちをなくすかについて、その大切さとその方法論について述べています。そして、おそらくは皆さんの私生活やビジネスシーンでも当てはまる場面があるのではないかなと思います。
「提案書を作成するにしても完璧なものを初めから目指して作るのではなく、まずは粗くても作ってしまう」とか、「完璧なBCP文書を作ることを目指してやるのではなく、まずはとにかくワンサイクル回してしまう」とか…。アジャイルに近い考え方かもしれませんね。ちなみに、私にも、本を書くときは3割の品質で200ページをさっさと1回書いてみるというアプローチをとった時が、最も効果的・効率的だという実感があります。
もちろん、1つの成功の法則が世の中の全てに当てはまるということではないのでしょうが、皆さんが個人で目標を立てて動いたり、または組織として目標を立てて動いたりしていく中で、こうした考え方も何かしらのヒントになるのでは?と思った次第です。
もし、ご興味のある方は、最近は翻訳機能も充実していますから、ぜひ、ご一読してみてくださいませ。
おっと、そうそう、忘れるところでした。本書のタイトルは以下です。
『Finish: Give Yourself the Gift of Done 』 Jon Acuff著



















