
大塚商会様
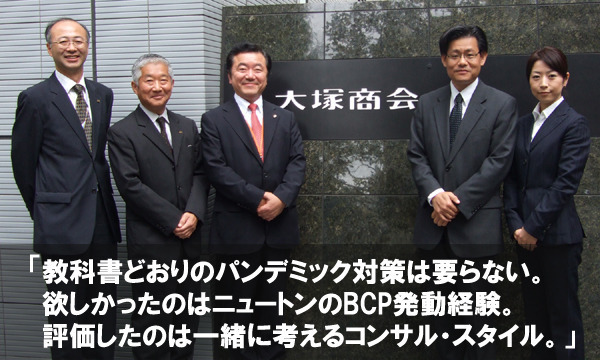
| お客様 |
取締役 上席常務執行役員 中嶋 克彦 氏 執行役員 人事総務部長 森谷 紀彦 氏 コンプライアンス室 部長代理 佐藤 憲一 氏 |
|---|---|
| ニュートン・コンサルティング |
代表取締役社長 副島 一也 |
株式会社大塚商会様は、システムインテグレーションやオフィスサプライの販売をワンストップで提供するユニークな業態の企業です。全国23の営業所および77万社の取引先をサポートするパンデミック対策プロジェクトについて、プロジェクトチームを牽引された取締役 上席常務執行役員 中嶋克彦氏、執行役員 人事総務部長 森谷紀彦氏と事務局をつとめられたコンプライアンス室 部長代理 佐藤憲一氏からお話を伺いました。
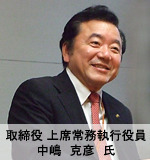
中嶋氏:「企業がオフィスで必要なものを全て提供する」というのが当社の基本事業です。具体的にはコンピューターシステムや事務機器、消耗品などをご提供することですが、当社はオフィスのワンストップソリューションとして、モノだけではなくメンテナンスサービスなどのヒトによるサポートも提供します。その事業スタイルの実現のために、全国で地域密着型の営業所を展開しています。
森谷氏:当社は1社で色々な事業形態を持っています。SIer、サポート、サプライヤーなどの個々の事業におけるコンペチターは存在するのですが、総体的に当社と同じ事業スタイルを持っている企業というのは他にないと思います。
中嶋氏:個々には似た事業を展開している企業はそれぞれあるので、そういう意味では、当社にとってはあらゆる企業が競合とも言えますし、あらゆる企業がパートナーともいえます。こうした事業形態は日本で当社だけではないでしょうか。
昔はこうした事業形態を否定的に評価された時代もありました。当時は企業は「選択と集中」が流行でしたから、「大塚商会は、提供する商品やサービスの範囲が広すぎて将来的には競争力を失う」と言われたりもしました。でも「お客様が困っていらっしゃることを何でも解決する」という基本方針が結果的に当社の長所となり、オンリーワンな企業に成長できたのだと思っています。
中嶋氏:本格的なリスク対策を考え始めたのは阪神大震災の時からです。それまでは停電時の対応マニュアル制定や火災訓練などはおこなっておりましたが、包括的な対策というまでには至りませんでした。
しかし、大震災が実際に起こってみて、事業活動の復旧に時間がかかったことや、社員の安否確認の方法が確立していないことが分かり、備えが足りないという反省の中から、ディザスターリカバリーを中心としたマニュアルを作成しました。
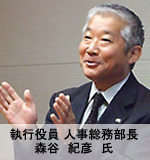
森谷氏:幸い、当社は社員も社員の家族にも死者は出なかったのですが、最後の1人の社員の安否確認が取れるまで丸2日かかってしまいました。社員が会社にどのように連絡を取るべきなのか、会社はどのように安否を確認するのかなど、早急に手順を定める必要があると痛感しました。
中嶋氏:一方でこうした災害時にはお客様も事業を再開したいというご要望が当社に一斉に入ってきます。当社としては、社員の安否確認と同時にお客様の事業再開のお手伝いを進めなくてはならないので、優先順位や手順を定めたものが必要です。
ただし、この当時作成したマニュアルは大規模災害を前提としていたので、その後はもっと多様なリスクに対応するためにマニュアルの改訂や通達の発信をおこなっています。大震災よりも単独ビルの火災や今回の新型インフルエンザなどのほうが発生確率はよほど高いので、対策はブラッシュアップが必要です。

佐藤氏:新型インフルエンザに限らず、当社がコンサルティング会社を利用する際に求めているのは知識と経験です。まず知識についてですが、今回のBCPもしくは新型インフルエンザ対応は新しい問題なので、当社を含めコンサルティング会社もどこも知識が少ないのは明白です。となると、今までの実績やその他コンサルティング事業からその会社の対応力を推測するしかありません。その意味では同様な分野で活躍されている候補が何社かあがりました。ニュートン・コンサルティングさんは候補の1社でした。
その中からニュートンさんを選んだのは、ニュートンさんには他社にない経験があったからです。実際に英国において、2005年のロンドン同時多発テロに直面し、BCPを発動された経験がある。また、石油タンク爆破事故にあわれた企業のコンサルサポートもしている。この経験は他の企業には真似できないわけです。
こうした経験があると、「こうあるべきだ」という一般論に基づいたトップダウン的なコンサルティングではなく、「今ある現実をどうするか」というボトムアップな提案をしてもらえるのではないかと感じました。そしてそれは今回の新型インフルエンザ対応という正に目の前にある危機に対応をしたいと考えていた当社の進め方とフィットしました。
佐藤氏:役員3名のスリートップが牽引するプロジェクトチームを発足しました。委員長は管理本部の中嶋、人事総務部の森谷、情報システム室の役員が補佐役となり、現場の実務代表者による総勢約15名のプロジェクトチームでした。
全体会議を月に2回実施し、個別チームが検討した内容の報告と次の課題の整理をするという手順で進めました。
中嶋氏:ただし、プロジェクトを進めている間でも、お客様からの要求は次々に出てきます。社会的重要度の高いお客様からは如何なる状況においてもサポートを継続することを誓約して欲しいと言うお申し入れがあったり、外資系の企業からはSLAの要求事項に対する回答書なども送られてきました。こうしたご要求、ご質問へのご回答はすぐにおこなわなくてはならないので、場合によってはいったん一定のご回答をした上で、再度協議すると行った柔軟な取り組みが求められました。

佐藤氏:弱毒性と強毒性の対応策を策定しました。具体的には、発生した際の初期対応から始まり、感染の拡大状況に応じてステージを区切り、対応内容を整理したマトリックス表を作成しました。
これに基づいて、社内の規定の整備をしました。一番上位の就労規則の細則からパンデミック対策基準、パンデミック対応の手順書や、特にお客様のサポートをする部隊であるコールセンター、データセンターや物流の個別の対策基準、運用マニュアルを策定しました。
そして、策定した基準や手順を就労者に徹底するために、就労者の目線で書いた通達や、ラーニング教材も作成しました。
中嶋氏:今回当社は弱毒性と強毒性の2つのパターンを作成したのですが、実際の状況はそんなに明確に2つのレベルで分けられるわけではありません。かと言って、全ての状況を想定したマニュアルを作成することも不可能です。その中で、現実とどうフィットさせるのか、というのは悩ましい課題でした。
実際社内で検討を開始した初期の段階では、参加者の「強毒性」「弱毒性」という状態に対する認識に幅があったり、「何とか事業を継続することが優先」から「社員の健康を守ることが第一義」まで価値観に相違があることで、とにかく議論が錯綜しました。それぞれが違うイメージを持って議論しているので、画一的なマニュアルに落とし込む作業は並大抵ではないなと感じていました。
そこをニュートンさんに議論に入っていただくことで、うまく取りまとめていただけたとお世辞抜きで思っています。
デジタルなアセスメントは重要ではあるけれどもいくらやってもキリがありません。また、パンデミックが発生した際にその過程でどのような事がありえるのかという知識も私たちには乏しいので、ニュートンさんがお持ちの想定マトリックス表を埋めていくという作業をすることによって、議論がスピードアップしました。無数にあるように見えるケースを軸で場合分けして対策を決めていったわけです。
森谷氏:実際には、マトリックス表と同じ状況になることはないかもしれませんが、想定した2つのパターンを元にその都度議論を行い、対応することにしました。大きな視野で検討しているので、対応力の高いマニュアルができたことと、一度社内で協議をしていることで、マニュアルと異なる事態が発生してもその時は議論がスムーズに進むだろうと思っています。
中嶋氏:少し話がそれますが、今回パンデミックの対応を検討した中で、当社の事業継続は引いてはお客様の事業継続につながるということを改めて強く感じました。当社はハブのような役割をしているので、お客様に当社がサポートを提供したくても、当社のサプライヤーからの納品が滞ってしまえば実現できません。対策においてはサプライチェーンの端から端までを検討しなくてはならないほか、77万社いるお客様に当社の取組みをご理解いただく必要もあるわけです。当社の利害のみ考えるような対策ではいけないのです。
中嶋氏:今回のプロジェクトではインフル対策に手抜かりがあってはいけないので、認証取得が目的になり本末転倒になってしまわないようにという事はしつこく社内で徹底しました。なので、検討の段階でもあまり規格にこだわらずに進めたつもりだったんですが、実はできあがったものは大枠ではBS25999に準拠して作成されていると後から知りました。
佐藤氏:プロジェクトを進める中で、われわれはあくまでも目前の状況に対してどのように対応するのかを検討しているという意識でしたが、同時に、ニュートンさんは規格との整合性ということも意識してコンサルティングしてくださっていたんです。今後他のリスクに検討を広げていく際にも役に立つと感じています。
中嶋氏:私どもの目線で、私どものことをよく分かってアドバイスしていただいたという意味において理想的なコンサルティングをおこなっていただいたと思っています。
今まで色々な規格認証を取得し、その際に様々なコンサルティング会社さんとお付き合いしてきましたが、ものすごく厳しく「こうあるべき」と言われることもありました。そういうときは自分たちの現実と違う、と感じることも多かったんです。でも、今回のように、決めるそばから状況がどんどん変わっていくこともあります。ニュートンさんにはその変わりゆく状況にも対応するアドバイスをいただけました。
森谷氏:私は人事総務部として、プロジェクトで決定したことを実際に社内に行動としておろさなくてはならない立場です。でも、コンサルティング会社の要求を受けてマニュアルや規定を作成はしたものの、いざ手順通りに行ってみると現実に適合していない様な事がよくあります。その点、ニュートンさんは作成したマニュアルを元に、では、具体的にどのように行動に落とし社内に伝達すると効果的かというところまで、的確なアドバイスをしていただけたので、その後の作業もスムーズでした。
中嶋氏:あとは、少し僭越になってしまうかもしれませんが、今回の案件に関しては、双方に勉強になったのではとも感じています。当方がない知恵を絞って「こう考えました」と報告すると、ニュートンさんが「そんな方法があったのですか。いいですね。もうひとつこういう方向からも考えてみてはいかがですか」と提案してくれる。「法的にこういう事も考慮しておいた方が良いのでは」と更なるアドバイスを下さる。
そういう柔軟な姿勢があったことも、今回のプロジェクトがうまくいった要因のひとつだと感じています。
失礼な言い方かもしれませんが、途中からは社内の人間のように感じていました(笑)。社内の文書なども全てお見せして、一体感を持って進めさせていただきました。
佐藤氏:繰り返しになりますが、ニュートンさんには一緒になって勉強しようという意識があったのが素晴らしかったと感じています。コンサルだからといって「こうしなくちゃならない」と言われてしまうと企業側としては「自分達のことをわかってくれていない」と感じてしまうのですが、解らないところをお互いに見つけだしては解決方法を検討する。そういう姿勢はとても嬉しかったです。
また、私は社内のみならず当社がソリューションを提供しているお客様に対してもこうした取組みをご紹介していく立場にあります。その際に「人に安心を。企業に信用を。」というキャッチフレーズを使っているんですが、実はこれはコンサルタントの高木さんが、あるとき会議の中で言われた言葉から借りています。これ以外にもサポートをしていただく端々で気持ちのこもった言葉をたくさんいただきました。
中嶋氏:他社のノウハウやアイディアを求めた方がはるかに早く進むと思います。事業は企業ごとにそれぞれ違いますが、事業継続や社員の健康維持、連絡方法などは会社ごとにそこまで違う話ではないと思います。真っ白な状態から自分たちで作られるのは大変だと思います。きちんとノウハウのあるコンサル会社などを巻き込んで進めたほうが、結果的にはコストも時間も抑えられると思います。
当社の初期の頃みたいに色んな人が色んなことを言って、2時間かけて議論したけれど何も決まらなかった、というようなこともしなくて済みますよね。
森谷氏:自社内で作ろうとすると自分たちの知っている範囲内での施策になります。もう少し大きな視野で抜けているポイントがないかということを確認しながら作ったほうが、何かあったときにも対応力の高い施策が講じられるのではないかと思います。
| 名称 | 株式会社大塚商会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋2-18-4 |
| 設立 | 1961年7月17日 |
| 事業内容 | システムインテグレーション事業/コンピュータ、複写機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など サービス&サポート事業/サプライ供給、保守、教育支援など |
| 利用サービス | 新型インフルエンザ対策サービス |
企業文化に根ざしたパンデミックBCPをご支援
弊社がご支援に入らせていただいた今年の7月以降、国内での感染拡大が進み、毎日状況が変わるという緊迫感のある日々をご一緒させていただきました。今回のお取り組みで特筆すべきは、①お客様の意思決定とそれを実行に移すスピードが非常に速かったこと、②プロジェクトメンバーの皆さんの当事者意識が非常に高かったこと、です。
プロジェクト会議には、常務をはじめとする経営陣と、主要な業務部門の代表者様が欠かさず出席されていらっしゃいました。そして毎回、弊社からのご提案に対して、その場で次々と新しいルールが採用され、数時間後には全社に向けてアナウンスされる、というスピード感。
また、会議では毎回活発な議論が繰り広げられ、「こんな要望が上がっているから反映してほしい」「この基準は業務の実態に合わないため、一律適用ではなく柔軟な適用に」など、この取り組みを我がこととして真剣に取り組まれる熱意が伝わってきました。
迅速な意思決定と実行力、そして真摯な当事者意識、このような素晴らしい文化をお持ちの企業様とご一緒させていただけたことを、心から光栄に思います。どうもありがとうございました。
