
東日本大震災では、一時的な公共交通機関の全面停止に伴って主要駅周辺だけでも2万人以上の帰宅困難者を生み出しました。しかし、結果的には同日中に電車の一部運行が再開されたこともあり、8割の人が帰宅できたと言われています。一方、東京都心部やその周辺直下を震源とする首都直下地震が発生した場合、被害の規模や交通機関の復旧状況は大きく異なります。
東日本大震災を機に策定された帰宅困難者対策ガイドラインにより、企業には「一斉帰宅抑制」が求められています。それでも帰りたいという社員とどのように向き合うのか。帰宅トリアージについて解説します。
軽視できない帰宅困難者問題
決して忘れてはならないのが、東日本大震災は首都圏を直撃したものではなかったという事実です。向こう30年以内に70%の確率で発生すると言われている首都直下地震(都心南部直下地震)は、東京都内の約6割が震度6強以上(最大震度7)と想定されています。交通機関の麻痺の程度やけが人の数は、東日本大震災の比ではないことが容易に想像できます。
表 東日本大震災発災時の東京都の被害状況と、都心南部直下地震発災時の被害想定の比較
| 東日本大震災 東京都の被害状況 | 「都心南部直下地震」による被害想定 | |
|---|---|---|
| ライフライン | 被害は少なかった | 上下水道断水、大規模停電発生、ガス停止 |
| 道路 | 一部液状化、ほとんどが歩行可能 | 沈下や隆起、陥没、土砂の流れ込み、液状化 |
| 火災 | 発生は少なかった(35件) | 延焼の恐れ |
| 電灯 | 一部停電、しかし街は明るかった | 大規模停電が発生し夜の街は暗闇に |
| 避難所 | 受入施設1,030カ所、会社など | 避難所不足の恐れ |
| 通信 | 輻輳はあれど、メールは機能 | 通信できずメールも使用しにくい |
| 心理 | 悲壮感はなかった(個人的感想) | 焦燥感と疲れ、進行鈍化によるイライラ |
| トラブル | (未確認) | 家屋倒壊による圧死、略奪 |
| 支援 | 飲料水購入も可、トイレ使用可 | 飲料水の確保困難、トイレ使用不可 |
上記表からも分かる通り、都心南部直下地震発災時には首都圏は甚大な被害が見込まれます。企業は帰宅困難者に関わる問題を重くとらえ、今から必要な対策をとっておくことが求められています。
“3日間は一斉帰宅抑制”が帰宅困難者対応の基本原則
このような大規模地震が起こった際の企業における大原則は、「むやみに帰宅せず、社内待機を行う」です。
東日本大震災を機に内閣府にて策定された「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策ガイドライン」に初めて明記され、その後、「防災基本計画」でもその方針が明文化されました。また、東京都では条例も制定され、企業に対し、発災後3日間は従業員の不要な移動を控え、事業所内での待機を促すとともに、従業員の安全確保のために3日分の備蓄品を整備するよう求めています。
3日間の一斉帰宅抑制を行うことは、「社員の命を守ること」「地域に迷惑をかけないこと」のために非常に有効な対応です。
調査によれば、帰宅困難者全体の3割の人を翌日帰宅させるだけで、危険な道路(満員電車状態の道路)を歩く時間を半減させ、5割の人を翌日帰宅させることで、この時間をさらに3割にまで減らすことができるといわれています。
仮に数十万人の人が一斉に道に溢れかえり四方へ歩き出したとします。道路は言わば満員電車と同じような状態になり、多くのけが人を出すなど二次災害を引き起こす可能性を十分に持っています。その上、万が一けが人が出たとしても、混乱の最中に救急車の助けを期待することは不可能です。
また、運よく自社の社員が無事に歩いて帰ることができたとしても、道路を多くの人が占拠することで、救援物資の運搬や救急車両の走行の妨げとなってしまいます。このような事態は、治安を悪化させ、より一層の混乱を招く可能性があります。
「社員の命を守ること」「地域に迷惑をかけないこと」のために、各企業は、所在地の自治体が発表する情報を確認し、具体的な対策を検討する必要があります。
「それでも帰宅したい」という社員には「帰宅トリアージ」を
企業は「被災当日は帰宅させない」という方針を社員に明確に示す必要がありますが、一方で「どうしても帰りたい」「どうしても帰らなければならない」と声を上げる社員が出てくることも想定しなくてはなりません。
会社がそうした社員を強制的に拘束することは不可能であり、最終的な判断は、社員本人に委ねざるを得ません。ただ会社として、社員が危険を冒して人が溢れる道に出ていくのを、何もせずにただ送り出すだけで良いでしょうか。社員一人一人が冷静な判断をできるよう、また、安全に帰宅できるよう、間接的なサポートをすることが重要です。
救護活動において負傷者対応の優先順位をつけることをトリアージと呼びますが、帰宅困難者本人が自らの帰宅優先順位を判断できる、いわゆる「帰宅トリアージ」の方法を社員に示してあげることも、企業ができるサポートの1つです。
「帰宅トリアージ」とは
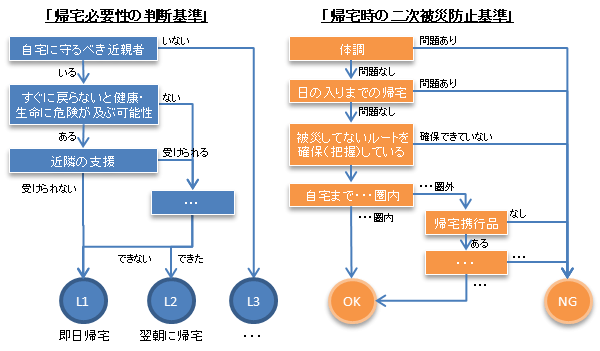
「帰宅トリアージ」とは、社員自らが帰宅判断を行えるようにするための判断基準です。帰宅者に優先順位をつけるためには、「帰宅の必要性」と「帰宅する際の被災リスク」の2つの要素を検討することが必要です。
「帰宅の必要性」とは、本人が早急に帰宅しなければならない理由に、どれだけの妥当性があるか、ということです。たとえば、自宅に幼い子供や要介護者がいる社員は、そうでない社員に比べて、より早急に帰宅する必要性が高い、と考えられます。
「帰宅する際の被災リスク」とは、帰宅途中で本人が二次災害に巻き込まれる危険性を指しています。たとえば、本人の健康状態が極めて悪い場合、途中で遭難する可能性があります。また、自宅までの距離が遠いにもかかわらず、道のりを全然把握できていない、あるいは、十分な装備ができていない、といった場合もそのリスクが高くなります。
こうした2つの観点を用いて、社員自らに「帰宅トリアージ」をさせることで、不必要な帰宅を思いとどまらせることができ、かつ、帰宅すると決めた社員に対しても被災リスクを軽減させることができるわけです。
社員が帰宅することを選択した場合には、注意事項を伝え、備蓄品を分け与えるなど、安全に帰宅できるよう配慮しましょう。また、帰宅した社員を一覧で管理する、帰宅時には報告させる、などの手順も用意しておくとよいでしょう。
帰宅困難者対応は平時からの取り組みが必要不可欠
どれだけルールを明確にしていたとしても、災害時に冷静な判断をいきなり求めることは非常に困難です。まず企業は、平時から、災害時の社員一人ひとりの対応がどれだけ社員本人そして地域全体に対して影響をもたらす可能性があるのかということを理解させるとともに、「被災当日に帰宅することのリスクは非常に高いものであり、少なくとも当日は会社にとどまらざるを得ない可能性が高い」ことへの心構えをさせる活動をしておくことが重要です。
あるアンケートでは、家族の安全が確認できれば会社に留まると多くの人が回答しています。社員に家族との安否確認方法を相互認識させることも、企業ができる活動の一つです。例えば、社員が自宅に帰宅出来ない場合に備え、家族内の安否確認方法や備蓄品の整備などのコミュニケーションを促すことも有効です。
また、企業としてはいざ社員を社内に滞在させるとなった時の準備も必要です。社内残留する社員の健康や安全、プライバシーなどに配慮した設備や備蓄、ルールの決定、外部から自社内に避難してくる一般人の対応方法等、あらかじめ準備しておくことが望ましいでしょう。
災害が起こってからでは、遅いのです。今、企業は、その責任を果たすために、こうした課題に積極的に取り組むことを強く求められています。






















