
日本精工 様
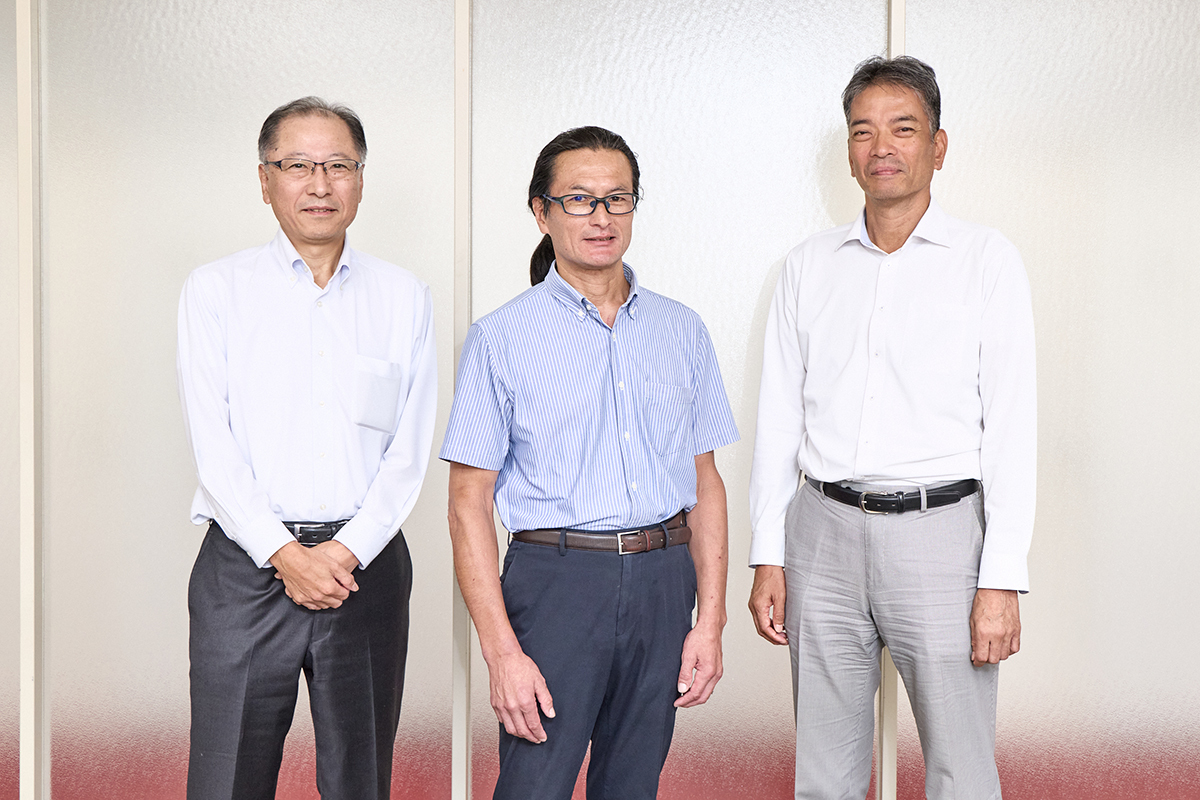
| お客様 |
生産本部危機管理推進室 グループマネージャー 阪下 健作 様 生産本部副本部長 杉村 博郎 様 生産本部危機管理推進室 室長 坂田 禎智 様 生産本部危機管理推進室 課長 大片 政人 様 生産本部危機管理推進室 大津駐在 シニアアドバイザー 山口 登志樹 様 生産本部危機管理推進室 シニアアドバイザー 端山 恵介 様 |
|---|---|
| ニュートン・コンサルティング |
シニアコンサルタント 辻井 伸夫 チーフコンサルタント 梅林 澄人 |
産業機器や自動車など、あらゆる機械に不可欠な部品である「ベアリング(軸受)」。軸の回転を支え摩擦を減らすことで、機械の高性能化や省エネに貢献します。日本精工様は、1916年に日本初のベアリングメーカーとして創業し、国内シェアNo.1、世界シェアNo.3を誇る総合ベアリングメーカーとして業界を牽引し続けています。現在では、ベアリングのほかにも自動車部品や精機製品(工作機械、産業用ロボット)の製造・販売まで幅広く手掛けています。
このたび、ニュートン・コンサルティングの「BCM/BCP改善・再構築支援サービス」をご利用いただいた経緯や成果などについて、阪下 健作 様(生産本部危機管理推進室 グループマネージャー)にお話をうかがいました。
阪下:当社の事業を大きく分けると、産業機械事業・自動車事業の二つです。産業機械事業では、一般産業向けのベアリングや、精密機器関連製品を製造販売しています。自動車事業では、自動車や自動車部品メーカー向けのベアリング、自動変速機部品やステアリングなどを製造・販売しています。
当社の事業の基盤となっているのは、「トライボロジー(物質間の摩擦をコントロールする技術)」「材料技術」「解析技術」「メカトロ技術」という4つのコア技術と、コア技術をかたちにするための高品質な生産技術です。これらを駆使しながら、製品の耐久性向上、高精度化などを実現し、幅広い産業の発展に貢献しています。
また、1960年代初頭から海外進出を進めてきた当社は、現在、国内外における30以上の国・地域に85カ所の生産拠点と200カ所以上の事業拠点を有しており、グローバルに事業を展開中です。
阪下:東日本大震災の発生時、当社は福島の工場が被災しただけでなく、関東圏内の事業所やサプライチェーンも甚大な影響を受けました。震災前から危機管理対策には全社的に取り組んでいたのですが、震災後はその教訓をふまえてあらためてBCPを作り直し、さらなる対応強化を進めてきました。具体的には、地震の事前対策・初動対応における課題の洗い出しや対策のほか、本社や各工場における事業継続課題への対応や事業継続フェーズの訓練など、精力的に取り組んできました。
長年にわたってさまざまなBCP活動を続けることができたのは、経営層に強い危機感と社会の要請に応えるべきだという会社としての使命感があるからです。「災害時などに当社の従業員を守ることは最も重要なことである。」「そして、当社の事業が長らく停止することは、世の中に多大な迷惑がかかるので、何としても避けたい。」という強い思いが原動力になっています。一方で現場はやはり、日々の業務に追われる中で、「まだ起こっていないこと」に備えるBCPについては優先順位がどうしても下がりがちでした。トップの思いを現場にどれだけ浸透させられるか、現場を巻き込めるか、というところは引き続き課題です。

阪下:経営層が参加する社内のコミッティで、「現状のBCP活動はどの程度有効なのか」という率直な投げかけがありました。東日本大震災から10年以上かけてBCP活動を深化させ、気象災害の激甚化・常態化や新型コロナウイルスの流行などさまざまな環境変化にも対応はしてきましたが、これまでの活動内容が現在も有効なのか、今の時代とマッチしているのかという点では確証が持てませんでした。そこで、従来のBCP活動の妥当性をあらためて検証するために、第三者からの評価を得たうえで、事業継続力をさらに高めたいと考えました。
阪下:当時、当社にはBCP活動推進にあたって、お付き合いのある会社があったのですが、今回は第三者の視点を入れたいと考えたので、別の会社にお願いしてみようという話になりました。そこで候補となったのが、ニュートン・コンサルティングでした。
ニュートンさんとはそれまで取引をしたことはありませんでしたが、さまざまなセミナーにもよく登壇している会社ですし、その存在は前々から知っていました。また、普段からBCPの情報を交換している他社のBCP担当者から、「ニュートンのコンサルティングサービスを利用したことがある」と耳にしたこともありました。最終的に、プレゼンで提案いただいた内容や、コンサルタントさんのコミュニケーション力も見たうえで、当社のニーズに合致したコンサルティングが期待できそうだと判断し、ニュートンさんへの依頼を決めました。
阪下:BCMにおける課題を明確にし、全社の事業継続力を高めるため、プロジェクトを3段階で実施しました。
まず第1段階(2023年8月~10月)として、BCM文書や活動の現状を評価しました。その結果、①復旧目標が過去の経験則に依存しており事業への影響とは別立てとなっている、②各対策が全社の復旧目標と連動していない、③対策が事前対策に偏っている、という3つの主要な課題が明らかになりました。
次に第2段階(2023年11月~2024年3月)ではこれらの課題に対応するため、分析に基づいたトップダウンでの方針決定を行いました。トップインタビューや経営層へのワークショップを通じて、当社の事業環境を踏まえたリスク分析、事業停止が許容される期間と目指すべき事業継続目標などを議論し、事業環境も踏まえ、有事における全社で統一された基本方針を事業別に定めました。
第3段階(2024年4月~11月)では、決定した方針に基づき、産業機械事業・自動車事業の2工場で2回ずつワークショップを実施しました。現場関係者と議論を重ね、重要事業を目標通りに復旧させるための具体的な業務レベルでの復旧対策、および実行上の課題を取りまとめました。現場の課題感などを丁寧にすり合わせることで、現場にとっても納得感の高い取り組みに発展させることができたと考えています。

阪下:目標としていたBCP活動の妥当性の検証と改善が実現できたと考えています。具体的にはまず、復旧目標を見直すことができました。当社にはもともと復旧目標があったのですが、これは東日本大震災の経験則によるもので、分析や明快な根拠に基づいたものではありませんでした。さらには「いつから起算しての目標なのか」といった定義も曖昧にしていました。こうした中、今回のプロジェクトでは、トップインタビューや経営層ワークショップを通して「復旧目標は、インフラが復旧し従業員が出社できるようになってからを起点とする」ことに引き直しました。それを受けて実施した現場のワークショップでは、「新たな目標達成度を100%に近づけるためには何をすればよいか」を洗い出しました。昨今の事業環境の変化を踏まえ、現場も納得感を持って現実的な検討ができ、その結果、復旧目標の意義について、現場層もしっかりと理解することができたと思います。
また、これまで各現場が良かれと思って取り組んできたことは多数あったのですが、BCM評価では「それらの対応が復旧目標を達成するためでなければならない」という認識がやや薄かった…という課題も見えてきました。結果的には、従来の各対策・活動は目標達成のために有益なものであり、続けていくべきであるということが検証でき、「やはり、これまで続けてきた対策は必要だったのだ」という納得感につながりました。そして、ワークショップを通して今後必要な新たな対策も洗い出すことができたのも成果といえます。
一方で、事業継続力の評価という性質上、現時点の現場の実力値を定量的に図ることはできませんでした。プロジェクトで洗い出した課題をやり切ることで、限りなく目標達成する可能性が100%に近づく、ということで、経営層や現場には納得してもらっています。
阪下:BCPを策定する上では、「○○という災害が起きたら△△という状況になるから、こういった対応が必要になるだろう」という「事象別のBCP」と、「人が出社できなくなったら?」「設備やインフラが使えなくなったら?」といった経営資源の使用に制約が出ているということを出発点とする「リソースベースのBCP」があります。個人的には、事象別/リソースベースの考え方をフレキシブルに組み合わせるのがよいと思っていますが、従来の地震一辺倒のリスク対応ではなく、リスクが多様化している中、このたびのプロジェクトはオールハザード対応を目指してリソースベースの考え方に基づいて進めました。当社の欧米拠点の担当者と話していると、当然のようにリソースベースのBCPを考えており、日本でもリソースベースの考え方が広まっていくのではないかと考えています。
当社ではもともと、東日本大震災を契機にBCP活動を発展させたこともあり、事象別BCPを推進していました。今回のプロジェクトでリソースベースに切り替えるにあたり、経営層・現場層に対しても、異なる思考法を理解してもらい、慣れてもらうことに苦労しました。ワークショップでも、限られた時間でレクチャーするのが大変でしたね。ファシリテーターを務めたコンサルタントの辻井さんにもご尽力いただき、結果的にはリソースベースBCPの手法が参加者たちにも理解され、それに基づいて議論することができました。現場責任者からも「これまでもやもやしていたものが、事業継続に必要な全てのリソースを洗い出して対策を検証したことで、もやもや感が解消された」との声もありました。

阪下:プロジェクトの流れは頭では理解できていても、いざ実行するとなると困難であることが多いです。その点、ニュートンさんにご用意いただいたツールに則って進めることができたので、事務局としては助かりました。特に、復旧目標を見直して新たに定義する作業は、経営層も巻き込んだ上で全社の合意を取る必要があったため大変でしたが、ニュートンさんの推進力のおかげで遂行することができました。1年半にも渡るプロジェクトを、社内のメンバーだけで行うのはなかなか難しかったと思います。
ワークショップでも、経営層や現場層に対して各プロセスについてかみ砕いて説明してくださり、事後アンケートでは参加者から「内容を理解できた」という声が多く寄せられました。
欲を言えば、びっくりするような対策事例などの紹介も期待していたのですが、そのような驚きはなかったというのが正直な想いです。裏返しにすると、当社では世間で実施しているような対策はほぼほぼ実施している、ということなのかと思っています。
阪下:今回のプロジェクトを通して、新たに設定した復旧目標達成を意識した対策について検討を重ね、「大災害が起きたら、これだけの死傷者が出る可能性もある」といったリアルな想定もしたことで、経営層や現場の間での危機感がさらに高まったと感じます。洗い出された課題のいくつかは、既に認識していたハードルの高いものもありますが、今後はそれらの課題に準じて粛々と対応を進め、事業継続力のさらなる強化を目指していきます。

※取材は2025年8月に実施。記事内の所属先および役職名は、プロジェクト当時のものです。
| 名称 | 日本精工株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎1-6-3 (日精ビル) |
| 創立 | 1916年11月8日 |
| 事業内容 | 産業機械事業(一般産業向けの軸受、精密機器関連製品の製造販売)、自動車事業(自動車及び自動車部品メーカー向けの軸受、自動変速機部品及びステアリング等の製造販売など) |
| 利用サービス | BCM/BCP改善・再構築支援サービス / BCP(事業継続計画)評価サービス |

シニアコンサルタント
辻井 伸夫
産業の基盤を支えるベアリング製造を維持・継続するために、実質と活動を重視するBCMを推進
日本精工様のプロジェクトは、2023年8月から始まりました。
プロジェクト開始時に約40種類のBCM関連資料(社内規程、過去のコミッティーや訓練実施結果の資料、工場の防災対策資料やBCP診断結果等)を開示していただき、内容を確認させていただきました。その際に気づいたことがあります。「形式的なマニュアルやチェックシートの類がない」ということです。
ISO22301の規格や内閣府のガイドライン、ネットから得られるサンプル文書をコピーしてマニュアルとしている企業が少なからずある中で、日本精工様は形式より実質、文書よりも活動を重視しているということが、開示していただいた資料からよくわかりました。
その後、社長様のインタビュー、経営層の皆様のワークショップ、そして2つの工場での現場の方々とのワークショップとプロジェクトを進めていく中で、事務局の皆様からお聞きする日頃の活動内容と、ワークショップ参加者全員が具体的な意見や課題を出し合い真剣にひざ詰めの議論を行う姿から、その感はより一層強くなっていきました。
このような実質重視、活動重視の姿勢は、今回の阪下様のインタビューでも改めて強く感じることが出来ました。日本精工様では今後も、形にとらわれず、自社にあったBCMの活動を力強く進めていかれるに違いありません。
