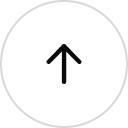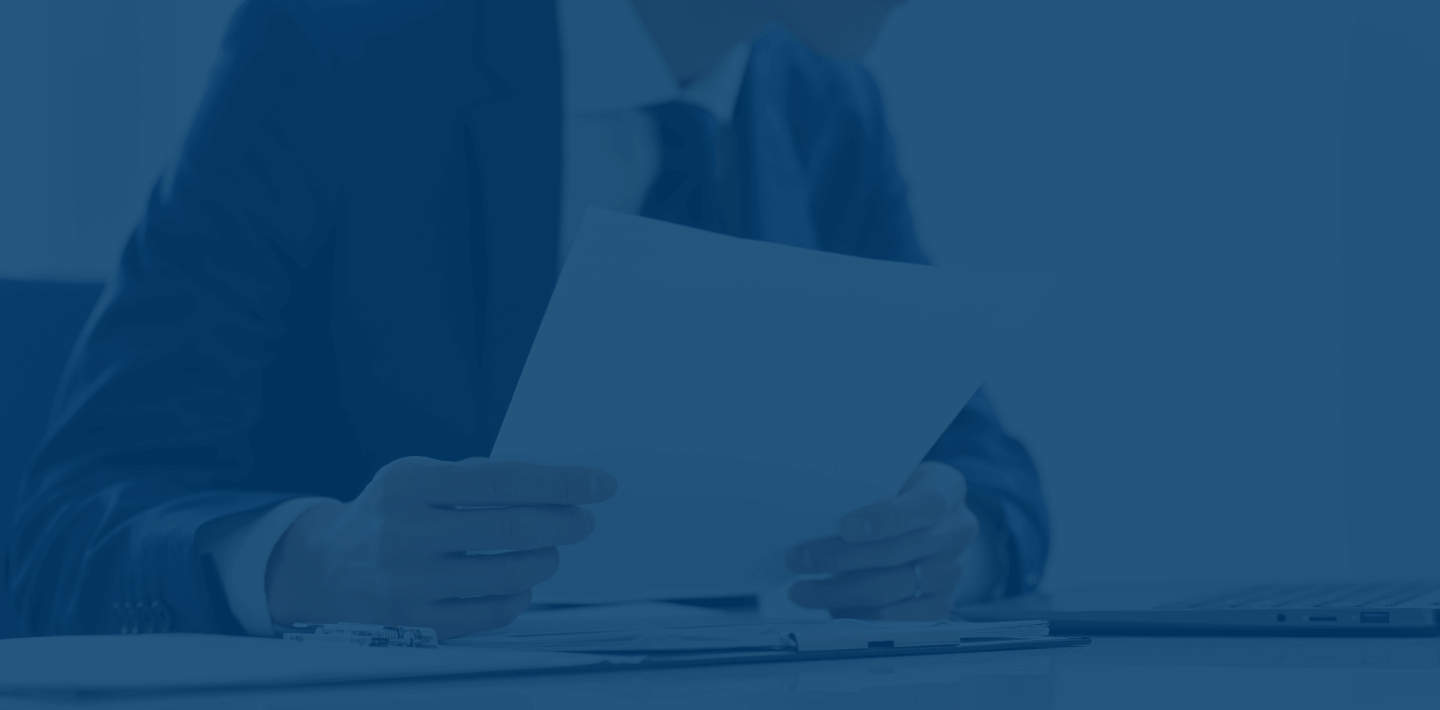サステナビリティ対応、開示だけで終わらせないために ~ERMとの統合管理の視点~

トランプ政権の復帰を受け、世界的にサステナビリティ関連の制度整備や投資の流れが一時的に足踏みしているようにも見えます。しかし、企業にとって「サステナビリティ」の重要性そのものが薄れたわけではありません。むしろ今こそ、自社の事業の持続可能性や中長期的リスクを見直す好機ともいえるでしょう。
本稿では、あらためて「サステナビリティとは何か」を整理した上で、全社的リスクマネジメント(ERM)との関係性、制度の最新動向を踏まえ、企業に求められる実務的な対応の方向性を解説してみたいと思います。
改めてサステナビリティとは
サステナビリティとは「持続可能性」を意味します。つまり、企業が社会や経済の変化の中でも、長期にわたって価値を提供し続けられる状態のことです。
かつては、企業が自社の利益や効率を最優先に考えることが主流でした。しかし今や、企業活動が地域社会や環境に与える影響が、企業の存続自体を左右する時代です。
例えば、過去にインドのある地域で飲料メーカーが工場を建設・操業した際、地下水の使用量を巡って地域住民との間で軋轢が生じ、最終的に工場の稼働停止に至った事例があります。企業側は「地下水の減少は気候条件や他の要因も関係している」と反論しましたが、結果的にこの地域では、企業活動が地域社会の信頼を失い、事業継続が困難になる状況となりました。たとえ法的に問題がなかったとしても、「地域社会への配慮を欠いている」と受け止められれば、企業のレピュテーションや操業そのものに影響が及びます。この事例は、まさにサステナビリティリスクの典型的な教訓といえるでしょう。
こうした事例は水資源に限らず、労働環境や人権、気候変動、資源の枯渇など、さまざまな分野で表面化してきています。
サステナビリティは一過性の流行ではなく、事業リスクや実害、さらには新たな機会として、企業の経営に直接影響を与えるテーマとなっていることは明らかです。10年後、20年後の企業のあるべき姿から逆算して、「いま何をすべきか」を考える — それがサステナビリティの本質です。
ESGとはどう違う?
サステナビリティと似た言葉に「ESG(環境・社会・ガバナンス)」があります。本来この2つは厳密には異なる概念ですが、最近では実務や報道の現場で、ESGという言葉がサステナビリティ全体を指すような形で使われることも少なくありません。
そもそもサステナビリティとは、企業が長期的に社会や環境と共存しながら価値を生み出し続けられるかという“経営の根幹に関わる視点”です。一方のESGは、主に投資家や金融機関が企業を評価する際に用いる「非財務的なリスク・機会」を捉えるための観点です。言い換えれば、サステナビリティは“何を実現すべきか”を示す経営の目的、ESGは“何を見られているか”を示す評価軸、ということになります。
例えば、ESG対応というと、気候変動対策の開示や人権方針の整備、ガバナンス体制の透明化など、「投資家目線での説明責任を果たすこと」に焦点が当たりがちです。しかし、ESGへの対応が形式的にとどまり、本質的な経営課題の解決や将来的なリスク低減につながっていなければ、サステナビリティの実現とは言えません。
企業のリスクマネジメントを担う方々は、こうした前提を踏まえ、自らが対峙する、あるいは使うESGやサステナビリティという言葉がどういう文脈・意図のものなのかを理解しておくことが重要です。
全社的リスクマネジメント(ERM)との関連性は?
サステナビリティやESGへの取り組みは、多くの企業において「サステナビリティ委員会」や経営企画・広報部門が主導し、一方で「全社重要リスク」の管理はリスクマネジメント委員会や内部統制部門が担う、というように、別々の仕組みとして運用されているケースが少なくありません。
この背景には、組織や制度の歴史的な経緯があります。サステナビリティは、もともとCSRや情報開示の延長線上で発展してきた領域であり、近年では、先のESGという投資家視点のキーワードにも象徴されるように、社外向けの説明責任や透明性を重視する「外向き」の活動として捉えられてきました。一方で全社的リスクマネジメント(ERM)は、法令遵守、業務継続、内部統制といった「内向き」の管理機能と密接に結びつき、社内のルール遵守や事業安定のための活動として発展してきたという違いがあります。
こうした流れから、両者が独立した委員会・評価軸で動いている現状は理解できますが、サステナビリティ関連のリスクや機会も、オペレーショナルリスクやコンプライアンスリスクも、本質的には“リスク”という共通のテーマを扱っているという点では変わりません。したがって、「絶対に分けて扱うべきもの」と考える必然性はなく、むしろリスクという切り口で統合的に運用・管理していくことが、企業のガバナンス強化の観点から望ましいといえるでしょう。
もっとも、運用の実態としては事情が異なる場合もあります。サステナビリティに関わる多くのリスクは、気候変動、資源制約、人権、レピュテーション、制度変化といった、企業の事業構造や中長期的な競争力に関わる「戦略リスク」に属します。こうしたリスクは、発生頻度や財務影響の定量評価が難しいという特徴があります。そのため、オペレーショナルリスクやコンプライアンスリスクとは異なるアプローチで取り組んだ方が管理しやすいのも事実です。
そのため、ERMの枠組みの中で、サステナビリティを含めた戦略リスクとそれ以外のリスクをどこまで統一したプロセスや体制で管理するかは、企業の裁量に委ねられます。こうしたリスクの統合的管理が機能するためには、経営者のリスクに対する考え方や企業文化、既存の戦略立案プロセスとの整合性に加えて、取締役会による明確な関与と意思の発揮が不可欠です。
サステナビリティを取り巻く情報開示制度と企業に求められる取り組み
さてここまでの背景を理解できると、昨今のサステナビリティ情報開示の制度化の意図や狙いをよく理解できるようになるでしょう。
サステナビリティ情報開示の制度化について、国際的には、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が企業に対し、「財務的影響をもたらす可能性のあるサステナビリティ関連リスク・機会」の開示を求める基準を公表しています。これを受けて日本では、金融庁のもとでSSBJ(サステナビリティ基準委員会)が基準策定を進めており、2025年度(2026年3月期)からの段階的な適用が見込まれています。初期段階では、まず上場企業や大企業を中心に開示が求められ、将来的にはより広い企業層へと適用が拡大していく見通しです。
これらの基準では、企業のサステナビリティ関連のリスクと機会が、経営戦略・事業計画・財務影響・リスク管理プロセスとどのようにつながっているかの説明が求められます。つまり、サステナビリティ開示は、もはや“IR資料の延長”ではなく、“経営そのものの可視化”が求められる段階にあるということです。
そのため、これまで多くの企業ではIRや広報が中心だったサステナビリティ対応が、今後は経営企画、リスクマネジメント、財務経理、サプライチェーン部門などを巻き込んだ“全社的な統合対応”に進化する必要があるともいえます。
サステナビリティ開示の制度化は、単なる報告義務ではなく、企業の経営基盤の見直しを促す構造的な変化です。この潮流を機に、ERMやサステナビリティ対応体制の再構築を進めていくことが、企業にとって持続的な競争力の源泉となるはずです。
ニュートン・コンサルティングでは「サステナビリティ・ERM統合支援サービス」や「SSBJ基準対応支援サービス」などを提供しています。