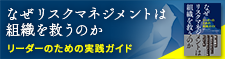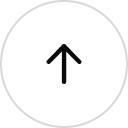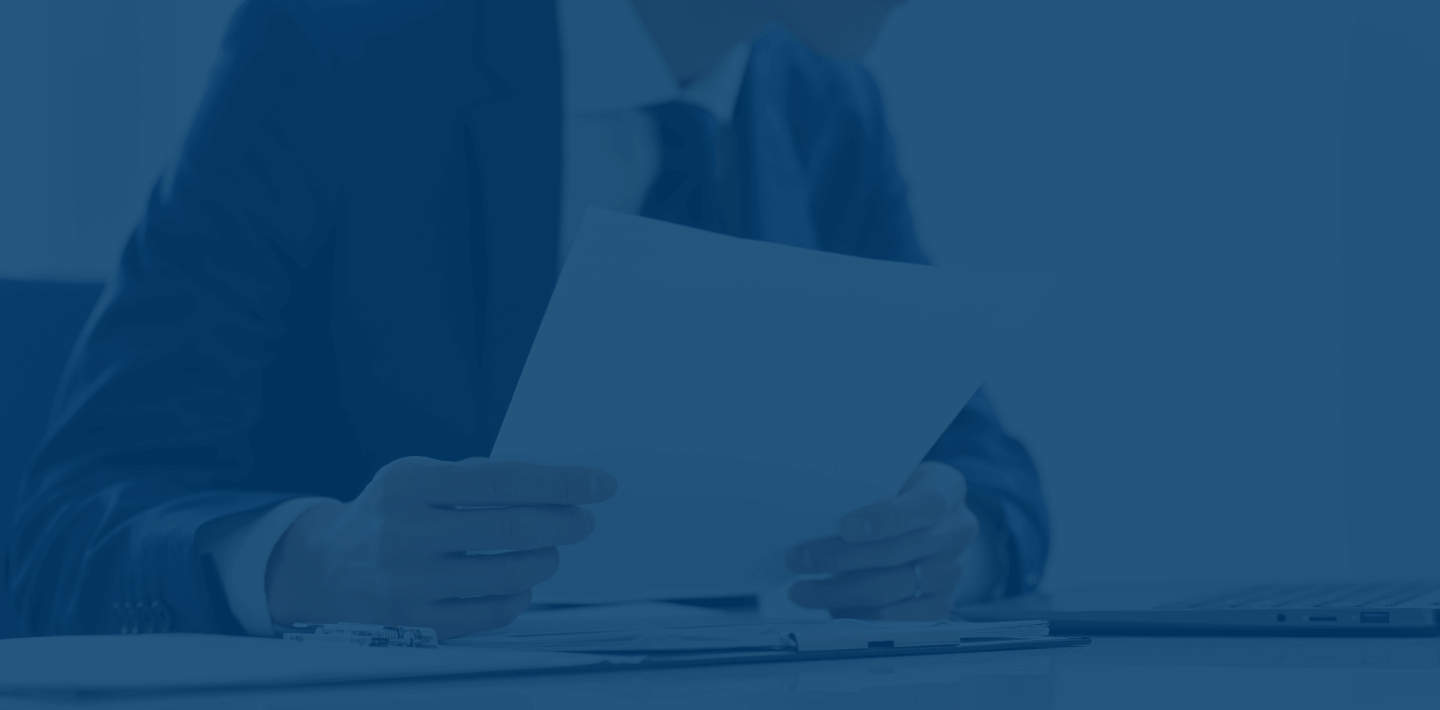政府の中央防災会議の首都直下地震対策検討ワーキンググループは19日、首都直下地震に関する新たな被害想定と対策の方向性をまとめた報告書を公表しました。首都圏で想定される複数の地震タイプのうち、首都中枢機能への打撃が最も大きい「都心南部直下地震」(マグニチュード7.3)が発生した場合、死者数は最大約1万8,000人、経済被害総額は約83兆円に上ると試算しました。今回の見直しは、国の「首都直下地震緊急対策推進基本計画」が2015年に策定されてから約10年が経過したことを踏まえたもので、政府は新たな想定をもとに同計画を改定します。
前回の被害想定の公表は2013年12月であり、12年ぶりの見直しとなりました。建物の耐震化や不燃化が進んだことで、全壊・焼失棟数は前回想定の最大約61万棟から約40万棟へと大幅に減少。これに伴い、地震の揺れや火災による直接的な死者は前回想定から約5,000人減り、経済被害額(資産等の被害と経済活動への影響)も前回想定の約95兆円から12兆円減少しました。ただ、道路や鉄道、港湾が復旧するまでの機会損失や迂回コストとして別途、約15兆円が発生するとも推計されています。
交通インフラへの深刻な打撃が想定されています。報告書は、平日の正午に発災した場合、鉄道の運行停止によって東京都内で約480万人、1都4県(神奈川・千葉・埼玉・茨城)では約840万人の帰宅困難者が発生すると試算しました。
帰宅困難者への対策として改めて従業員の一斉帰宅抑制の徹底を求めました。「帰宅」ではなく「施設内にとどまること(オフィス内待機)」を前提とした備えを求め、3日間分の備えでは不十分となる場合に言及しています。
テレワークや共働き世帯の増加といった近年の社会情勢の変化も反映されました。東京圏ではこの10年で6歳未満の子どもがいる世帯は1.27倍に増加しています。発災後に学校や福祉施設が休業すると、子どもや高齢の親の介護のために夫婦のいずれかが出勤困難になり、企業活動の支障となる恐れがあると指摘しました。コロナ禍を経て定着したテレワークが、出勤困難時や鉄道運休の長期化、広域避難の際にも事業継続の有効な手段であると位置づけられました。
一方で、テレワークは電力に依存する弱点があります。もし、長期間の停電や通信障害が発生すれば機能しなくなります。特に、東京湾沿岸の火力発電所が被災した場合、復旧に1カ月程度を要し、首都圏全域で電力需給がひっ迫する恐れもあると指摘しています。
通信インフラや電力への依存度の高さを踏まえ、企業に対しBCPの見直しを求めています。電力や通信、物流が長期間寸断される事態を想定し、本社機能そのものを一時的に首都圏外へ移転することを検討する必要があると明記しました。
また、近年は「災害関連死」にも焦点があてられるようになりました。報告書では初めて災害関連死を推計し、最大で約4万1,000人に達すると試算されています。高齢化や避難生活の長期化に伴うもので、直接的な死者を大きく上回る規模となる可能性が示されました。