一昨年の東日本大震災では橋の崩落により、避難および被災後の生活や復興および物流に大きな被害が発生しました。一般的に道路の復旧に比べ、被害を受けた橋の復旧には多くの時間を要するため、被災後に与える影響は大きいと考えられます。
ところで、あなたの自宅からの通勤ルートや避難場所へのルート、会社の材料や製品の輸送ルートに橋はありますか?その橋は、大きな地震でも大丈夫でしょうか。
道路橋示方書が10年ぶりに改定
昨年(平成24年)2月、国土交通省は道路として使うために設けられた「道路橋」の設計についての基準(道路橋示方書)を約10年ぶりに改定しました。東日本大震災を踏まえ、耐震性の基準を見直したほか、橋の維持管理に必要な設計図などの記録を保存することなどを盛りこみ、低いコストで長期間、安全にインフラを使えるようにするのが狙いです。同年4月1日から適用されています。
- 道路橋示方書(どうろきょうしほうしょ):
- 橋・高架の道路等に関する技術基準。国土交通省が定め、共通編・鋼橋編・コンクリート橋編・下部構造編および耐震設計編の5編で構成。必要に応じ、平成23年度以前の設計にも適用可能としている。
- 道路橋示方書の位置づけ:
- 政令「道路構造令」橋・高架の道路に関して、構造及び設計自動車荷重が規定。 省令「道路構造令施工規則」構造上の必要事項を明示。 技術基準「道路橋示方書」(道路局長、都市局長から整備局長等宛て通達)省令に準じた基準として運用。
改定されたポイントを簡単にご紹介しますと、下記3点が挙げられます。
1) 過去の地震を踏まえた設計地震動の見直し
日本の周辺には地震源となる大規模なプレートが存在し、直近に発生した連動型地震のデータから設計の前提とする地震動タイプが見直されました。その結果、東日本大震災や阪神大震災クラスの大地震がきても、橋が致命的な損傷を受けない設計が求められるようになりました。新たに、現在使用している鉄筋に比べ、強度が約1.4倍の新型鉄筋やステンレス鉄筋も使えるように改められました。
2) 設計施工上の配慮事項
地震の際に橋の両端の盛り土に段差ができないよう、コンクリートの板を埋め込む対策なども求めています。橋を溶接するときに、JIS等の専門知識のある技術者を現場に配置することを建設会社に義務付け、手抜き工事を防ぐことを目指しています。
3) 維持管理に対する考え方
設計段階から橋の維持管理のため設計図には、橋のたもとの地盤の固さのほか、橋脚の下に打ち込んだくいの種類、重点的に検査する必要のある箇所などを明記するよう求められ、工事記録を残すことにより、補修する際にも役立てるようにしています。
新指針対応に取り組み始めた自治体
昨年、道路示方書が改定されて以降、各都道府県では平成23年度以前に設置された橋(道路橋)の耐震性について調査し、必要な耐震補強に着手し始めています。インターネットで検索すると、補強を必要とする橋やその関連道路を含めた補強工事の状況や、3~5ヶ年計画で対象となる橋の補強工事計画などをホームページで公開している自治体もあります。
たとえば、兵庫県神戸市の例では、「災害時における緊急車両や救援物資の輸送路として位置づけられている緊急輸送道路上の既設橋梁の耐震補強を優先的に実施する」と計画の目的と該当するエリア内の対象道路を紹介しています。
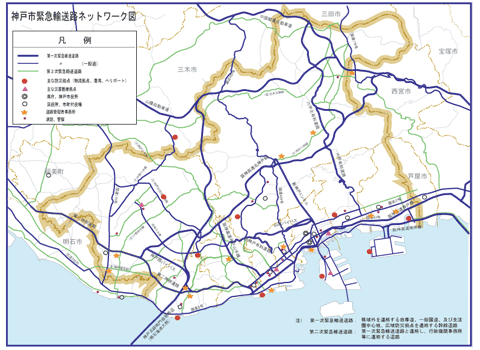
また、神奈川県川崎市のホームページでは耐震補強対象の一覧とともに下図のように具体的に紹介されています。

静岡県浜松市のホームページでは詳細な地図の上で、道路橋の耐震レベルや耐震補強工事の進捗を見ることが出来ます。

ご紹介した例の他にも、各自治体では東日本大震災を教訓に橋の耐震診断ならびに、補強が必要な橋について工事が進められています。これらの補強工事の進捗状況や工事計画の概要は、県や市町村および国土交通省地方整備局、国道事務所などのホームページや資料で知ることが可能です。
BCP策定時にも考慮したい「橋の影響」
一昨年の東日本大震災では甚大な被害が発生しましたが、震災後の短期間で東北沿岸部への道路交通機能が回復できた要因の一つに、橋梁の耐震補強により落橋などの致命的な被害が少なかったことが挙げられます。また、橋梁そのものが無事な状態であっても、橋台背面(道路と橋の境目部分)が崩落もしくは液状化による地盤沈下でズレが生じ、段差による通行不能となるケースも沿岸部などの埋め立て地や地盤の軟弱な場所で発生しています。今回の示方書に明記されている橋の盛り土対策により、このような被害の減少が期待されます。
震災発生時の避難路に橋がある場合、利用できるかどうか一度調べて安心するとともに、工場や倉庫の立地により橋の使用を余儀なくされる場合、被災後の業務の継続を検討する上で安全なルートの確保は必要です。
また、自社の近くに橋がなくても原材料および商品の仕入れ先が港湾や河川に近い場合、従業員の自宅から職場に向かう間に橋がある場合、その橋が通行不能となった場合、確実なルートを調べておくことは、対策を検討する上で重要です。
大震災からの復興とともに将来に向けた強い橋づくりが、全国で推進されています。あなたのまわりにある橋がどのような耐震性をもっているのか、調べてみませんか。






















