内閣府の南海トラフの巨大地震モデル検討会より南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高に関する第一次報告が平成24年3月31日に発表されました。今回発表された津波高などの数値は東日本大震災の教訓から、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を想定したこともあり、従来の中央防災会議の被災想定よりも大きな数値が算出されています。
南海トラフ地震とは
南海トラフとは駿河湾から九州にかけての太平洋沖のフィリピン海プレートと日本列島側のユーラシアプレートなどの大陸側のプレートが接する境界に形成されているトラフ(浅い海溝)のことです。過去、東海、東南海、南海地震の3つの震源域が同時あるいは一定の時間差を持って動くことによる地震が発生しています。
また、このエリアでは100年から150年程度の周期でマグニチュード8クラスの海溝型地震が発生しており、今後数十年内に発生が懸念されている大規模地震の一つと言われています。
被災想定について
今回発表された震度分布・津波高の想定がどれ程のインパクトなのか、イメージをつかみやすくするために中央防災会議(2003年)の被害想定と比較してみました。
【中央防災会議(2003年)との比較】
| 今回 | 中央防災会議(2003年) | ||
|---|---|---|---|
| 地震規模 | マグニチュード9 | マグニチュード8 | |
| 震度分布(面積) | 震度7 | 10県153市町村(約0.7万km²) | 7県35市町村(約0.03万km²) |
| 震度6強以上 | 21府県395市町村(約2.8万km²) | 9県120市町村(約0.5万km²) | |
| 震度6弱以上 | 24府県687市町村(約6.9万km²) | 20府県350市町村(約2.1万km²) | |
| 津波高 | 20m以上 | 6都県23市町村 | 0 |
| 10m以上 | 11都県90市町村 | 2県10市町 | |
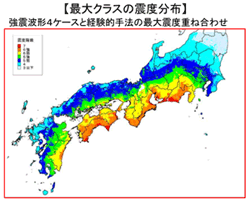
想定する地震規模がマグニチュード9に引き上げられ、震度分布についてはこれまで計測対象外であった地域が新たに加わわっています。北は福島県から南は鹿児島県まで幅広い範囲で震度3以上の揺れを観測すると予想されています。
また、津波高についてはこれまでになかった20メートルを超える津波の発生を予想するなど厳しい内容となっているだけでなく、震源が陸地に近い場合には1メートル以上の津波の最短到達時間が地震発生から2~3分とする予測も発表されています。
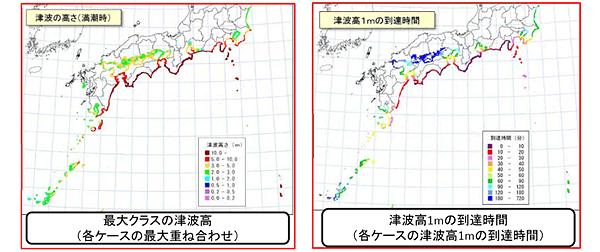
今後の発表
今回の発表されたデータは広範囲の領域の全体を捉えた防災対策の参考とするために推計したものです。より詳細な地域ごとの津波高、浸水域などの被害想定については6月頃までに建物被害や人的被害について推計し、その後、秋頃までに経済被害等について推計される予定となっています。





















