地震、爆発、火災、交通事故などは、発生確率こそ低いものの、起きてしまうと経営に深刻な影響を与えてしまいます。こうした事故災害リスクへの対応を二つのステップで紹介します。

発生確率は低いが経営に大きな影響を与える事故災害リスク
今回のテーマは事故災害リスクです。端的に言うと、「突然社長が死んだらどうする?」といったことです。また、ほかにも、地震や工場の爆発、火災などで社屋が被災し、社長のみならず、社員の多くがいなくなるということも起きないとは限りません。
こうしたことが起きる原因として、地震、爆発、火災、交通事故などが考えられますが、どれも発生確率は低く、普段あまり考えたくない事象です。しかしながら、ひとたび起きてしまうと経営に大きな影響を与えてしまいます。今回は、こうした事故災害リスクに中堅・中小企業がどのように向き合えばよいのか、シンプルに二つのステップでご紹介します。
ステップ1.何を対策するか決める
さて、自社ではどんな事故災害が比較的起こりそうで、また影響が大きいでしょうか? この辺りは、実は明らかに分かっていることも多いものです。例えば、工場で火災になりやすい工程があったり、工場が断層の上に立っていたり、川が近くにあり氾濫したことが過去に何度もあったりするなど、事故災害が起きてもおかしくない、気になる事象があれば洗い出しておきましょう。
また、どの事象が自社に与える影響が大きいかも検討しておきましょう。例えば、「地震と水害は起こりうるし看過できないので、会社としてリスク管理の対象にする」といった具合に、何について対策するのかを決めておくのです。
ステップ2.対策する
次に、決めたリスクに対する対策をしていきます。対策とは主に、「予防低減策」、「発生後の行動計画」の二つです。
予防低減策
事象が発生しにくくしたり、発生しても影響が小さくなるようにしたりすることです。例えば、地震の対策ならば、断層のあるエリアから移転する、もしくはそれができないならば、耐震工事や転倒防止を行うなどの対策です。
発生後の行動計画
どこまで事前に対策をしても、何らかの事象が起きてしまえば、その状況で対応していくことになります。起きてからどう動くかを考えていては、後手に回ってしまい、人命を守れない、お客様にビジネスをご提供できない、結果として自社が立ちいかなくなるという困った事態が起きてしまいます。そのため、必要な行動計画を事前に検討し、その計画遂行に必要な人員を共有しておく必要があります。考え方を整理するために用意しておきたい三つの文書をご紹介します。
緊急時社員ハンドブック
地震や火災などが起きたら、どのようにして身を守るのか、会社との連絡はどうするのかなど、必要なことは決めておき、ハンドブックに記載して社員に持たせましょう。
対策本部マニュアル
会社として対応すべき事態が起きた時に、誰が対策本部長で誰がそのメンバーになるのか、またその際に対策本部で対応すべき役割は何なのかを明確にしておきましょう。また、この体制を考えるにあたり、代行者を決めておくことが重要です。
業務別の災害時対応マニュアル
自社でどうしても止めたくない業務や、担当者が1名で行っている業務などを洗い出し、業務マニュアルを作っておきましょう。例えば、受発注業務、支払業務などです。
最後に、社内のいろいろな業務が属人的になればなるほど緊急時対応は難しくなってしまいます。できる限り複数のスタッフで代行できる柔軟な業務体制を普段から意識しておくことが有効です。
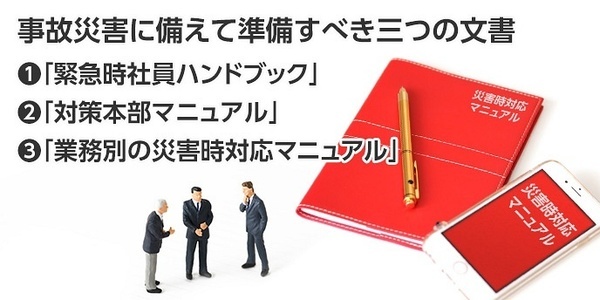
(大塚商会ウェブサイトより転載)





















