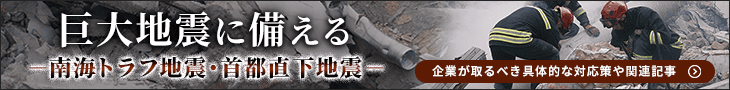みなさん、こんにちは。地震に敏感になる今日この頃ですね。
私はこういう仕事柄、普段から自宅などでも防災対策をしています。台所では食器棚、寝室では本棚などが倒れてこないよう突っ張り棒を取り付けてあります。マイカーは常に燃料が半分を下回らないよう意識しています。水とトイレ関係の備蓄は特に念入りにしています。土間には、水のペットボトルが入った段ボールが10ケース以上積み上がっています。水はローリングストックを採用していますので、1~2ヶ月に1回の頻度で買い足すようにしています。この原稿を書いている間にもいつものルーティンで近隣のスーパーに足を運んだところ、珍しく売り切れていました。
おそらくというか間違いなく南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」の影響でしょうね。気象庁は、巨大地震発生についていつもより数倍リスクが高まったとして被害が想定される地域の住民には1週間を基本として備えの再確認をした上で、通常の生活を続けるよう呼びかけましたからね。
さて、私も、手元の文献をひっくり返して南海トラフについて復習をしたところです。報道でも触れられていますが、今回の注意は成り行きで決められたものではなく、2019年から運用が開始された「南海トラフ地震臨時情報」に沿って行われたものです。南海トラフ沿いではマグニチュード(M)7.0以上の地震がこれまでに何度も起きており、最大津波高34mと最大震度7の地震が起きる可能性があると言われています。しかも、想定される震源域の全てのプレートが一斉にズレ動くのではなく、部分的にそのズレ動きが伝播すると言われています。つまり、段階的に巨大地震がやってくる可能性があるということです。ちなみにこのことを学者やメディアは「一部割れ」や「半割れ」と呼んでいます。最初に全体の一部または半分が割れてその後、残りが割れるというイメージです。今回は「一部割れ」と評価され、「一部割れ」の後にM8以上の地震が発生する確率は、「数百年に1回程度」とされています。この頻度はいつも(=千年に1回程度)より数倍高まったことになります。これが「巨大地震注意」が発表された背景です。
そして、言わば「一部割れ認定」をされたのが8月8日に宮崎県日向灘で起きたM7.1の地震です。幸いなことに、この地震が発生してから1週間が経過し「巨大地震注意」は取り下げられましたが、当然のことながら企業も個人もガードを下げることはできません。今回、南海トラフ巨大地震が起きなかったということは、ひずみエネルギーが未だ蓄積されたままであるということであり、この先のどこかで、そのエネルギーが解放されるきっかけがやってくるだけのことだと考えられるからです。しかも宮崎県日向灘の地震に対する「一部割れ認定」が取り消されたわけではありません。というのも、南海トラフ地震発生の可能性があるのは近隣の地震後1週間とは限らないからです。最初の1週間こそいつもより発生可能性が高いということで注意喚起がなされましたが、過去のデータによれば最初の地震から2年後に南海トラフ地震が発生した場合もあります。具体的には、1944年のM7.9の昭和東南海地震ではその発生から何と2年ちょっと経過してからM8.0の昭和南海地震が起きているのです。
とは言え、こうした南海トラフ地震への警鐘は世の中の識者やメディアの誰もが行っていることでしょう。重要なことですので、ここで私が改めて触れること自体にはそれなりの意義はあると思っていますが、私はむしろ、南海トラフ地震の影響域外の方々に警鐘を鳴らしたいと思っています。
なぜ?と思われるかもしれませんが、過去の地震を振り返れば、「えっ!?今、そこっ!?」という場所で地震が発生していることの方が多いからです。しかも、不意のパンチをもらった時ほどダメージが大きくなるものです。心に隙がある時ほど、異常事態に直面した時の混乱は大きくなります。多くの人の目が南海トラフに注がれている今だからこそ、あえてその影響外にいる人もガードをあげるべきではないでしょうか。首都直下地震は相変わらず大きなリスクですし、日本は全国どこでも震度6弱以上の地震が起きても不思議はないと言われているくらいですから、それ以外の地域でも同様のことが言えます。例えば、このタイミングで日本海側や東北地方で大地震が起こることだってあり得ます。
じゃあ、気が休まらないじゃんと、そんな声が聞こえてきそうです。ちょっとぐらい緊張感を緩めさせてよ、とも。東日本大震災直後こそ、BCPの見直しや訓練に余念がなかった企業も、だんだん力が抜けて訓練がおざなりになっているのはそうした気持ちの表れでしょうか。しかし、自然は「ちょっと気が張っていたから一休みしよう」という人間の都合を聞いてくれるものではありません。ガードを上げていようが下げていようが、自然災害はいつだって容赦なく我々に襲いかかってきます。
だからこそ、今一度、今回の件をきっかけに緊張感を取り戻してほしいと思います。そして、どうやったら一度上げたガードを下げずにいられるかを考えてほしいのです。ちなみに私自身が持っている1つの答えは習慣化と他人ごとの自分ごと化です。冒頭で述べたような防災対策はもう何年も続けており習慣化しているものです。また一見、自分には関係のない事故や災害であっても、常にそれを自分に当てはめたらどうなるかを考えるようにしています。
より本格的なヒントを知りたい方は、弊社が出している小冊子「なぜ、年1回のBCP訓練・演習が時代遅れなのか⁉-2030年、企業のBCPはこう変わる-」や「BCP総点検のススメ~アフターコロナ・能登半島地震からのBCP再構築~」なども参考にしてください。ぜひ今回初めて出された「南海トラフ地震臨時情報」をきっかけとして、来たるべき将来の大災害に健全な緊張感を持って立ち向かえるようになって頂けたらと思います。