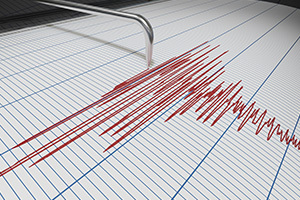
カインとは地震の強さを揺れの速度で表すもので、1カイン(cm/s)は1秒間に1センチメートル動いたことを意味します。
地震動の最大速度を表すもの
地震の大きさの単位としては震度、マグニチュードに加え、「ガル」がありますが、ガルが瞬間的な加速度であるのに対し、カインはこれに時間を掛けてエネルギーの大きさ、つまり地震の強さを示します。同じ加速度でも継続時間が長ければ、速度が増すことになりますので、地震が建物に与える影響を考えるときは、カインを用いるケースが多くなっています。実際に、ガルの大きさよりもカインの大きさの方が建物の被害状況と一致するとされています。
阪神・淡路大震災では犠牲者の90%が倒壊した家具や建物の下敷きによる圧死であったのに対し、東日本大震災では同様の被害がほとんどありませんでした。これは、木造家屋、非木造の中低層建築物が最も揺れやすい周期である1~2秒で東日本大震災は100カインであり、阪神・淡路大震災の200~300カインに比べて小さく、家屋被害がおきにくい揺れだったためと考えられています。
耐震設計とカイン
一般に、構造物の耐震設計を行う際、対応方法の違いから、想定する地震動を二段階に分けます。地震動レベル1を中規模の地震、レベル2を最大規模の地震とし、従来の基準は前者が「この構造物の耐用年数中に一度以上は受ける可能性が高い地震動」、後者が「その構造物が受けるであろう過去、将来にわたって最強と考えられる地震動」というもので、非常に抽象的な表現であったっため、設計者によって捉え方がまちまちになりがちでした。後に具体的な数値で表すようになり、レベル1を25カイン以上、レベル2を50カイン以上としたのです。
1994年以前の超高層ビルは、加速度400~500ガル、速度40~50カインで設計されることが多かったのですが、阪神淡路大震災がこれらをはるかに上回る800ガル、91カインであったため基準が見直されました。現在の構造設計では、最低でも50カイン、慎重な設計者は50~75カイン、ときには100カイン設計をうたい文句としている設計者もあります。ちなみに75~100カインの設計では建築コストが5~10%アップすると言われています。もちろん耐震性能は設計だけではなく施工によっても左右されますから、75~100カインであれば間違いないと言い切ることはできません。
いずれにしても、耐震設計を行う上で、地震動の破壊力を示す大きさとしてカインを用いることが多くなっているのは確かです。
過去の地震におけるガルとカインの比較
最大加速度と最大速度とは比例関係がないことがわかります。
| 地震名 | 最大加速度 ガル(cm/s2) |
最大速度 カイン(cm/s) |
|---|---|---|
| 1940年 エル・セントロ NS | 341.70 | 33.45 |
| 1940年 エル・セントロ EW | 210.14 | 36.92 |
| 1952年 タフト NS | 152.70 | 15.72 |
| 1952年 タフト EW | 175.95 | 17.71 |
| 1956年 東京 NS | 74.00 | 7.63 |
| 1962年 仙台 NS | 57.50 | 3.46 |
| 1963年 大阪 EW | 25.00 | 5.08 |
| 1968年 八戸 NS | 225.00 | 34.08 |
| 1968年 八戸 EW | 182,90 | 35.81 |
| 1978年 東北 EW | 202.57 | 27.57 |






















