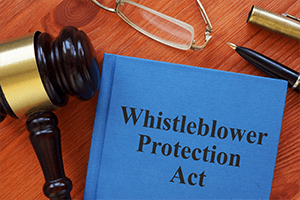
公益通報とは、労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員なども含む)や退職者(退職や派遣労働終了から1年以内)、役員が、役務提供先の事業者による一定の法令違反行為を通報することです。なお、不正の目的で通報した場合は公益通報にはあたりません。また、通報先は事業者の内部、権限を有する行政機関、その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合など)のいずれかです。公益通報者保護法は、公益通報をする人の立場を守るための法律です。
公益通報者保護法の目的
公益通報で企業の違法行為が明らかになり、その行為が改められることで、公益通報をした人(公益通報者)や勤務先、そして社会の安全が守られます。とはいえ、公益通報者が解雇などの不利益な取り扱いをされると、通報者が危険にさらされることになります。また、「通報することで不当な扱いを受けるのではないか」と公益通報を躊躇することで、結果として違法行為が放置されることにもつながります。
そこで、公益通報者を守り、国民生活の安全・安定と社会経済の健全な発展を図るために作られたのが「公益通報者保護法」です。公益通報をした人がそれによって解雇などの不利益な取り扱いを受けることがないよう、どのような通報を行えば通報者が法的に保護されるのか、制度的なルールが定められています。
改正公益通報者保護法の施行
公益通報者保護法は2004年6月に成立、2006年4月から施行されましたが、その後も事業者による不祥事は後を絶ちませんでした。こうした状況を受け、不正の早期是正、被害防止を図るため2020年6月に「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)が成立、2022年6月から施行されました。
改正公益通報者保護法では、「①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすく」、「②行政機関等への通報を行いやすく」、「③通報者がより保護されやすく」、という3つの狙いで改正が行われました。
①についてはまず、事業者に対して、内部公益通報に対応する体制を整備することが義務付けられました。具体的には、窓口の設定、調査、是正措置などが必要です(従業員数300人以下の中小事業者は「努力義務」となっています)。
また、事業者には、内部通報に対応する「従事者」を指定する義務が課されました。従事者は、公益通報者が誰なのかが分かる情報(氏名など)を漏らしてはいけません。この守秘義務には期限の定めがなく、異動や退職後も続くもので、破った場合には30万円以下の罰金が科されます。
さらに、法の規定に違反した場合は、助言や指導、勧告の対象になり、勧告に従わない場合に公表の対象になることとなりました。
②については、行政機関への通報が公益通報として保護される条件として、氏名などを記載した書面を提出する場合を追加しました。また、通報機関への通報の条件として、財産に対する存在や、通報者を特定させる情報が洩れる可能性が高い場合を追加しました。
また、③については保護範囲の拡大が多数行われました。例えば、保護される公益通報者の対象は、改正前は労働者のみとなっていましたが、改正後は1年以内の退職者や役員も追加されています。保護される「通報対象事実」の範囲も、犯罪行為に加えて新たに過料対象行為が含まれるようになりました。また、保護される通報については、刑事罰の対象に行政罰の対象が加わりました。公益通報に伴う損害賠償責任も免除されるようになりました。
さらなる見直しを求める動きも
改正法施行から1年半が経過した2023年度、消費者庁は民間事業者等における内部通報制度の実態調査を実施しました。調査の結果、従業員数300人超の事業者の91.5%が内部通報制度を「導入している」と回答し、2016年度調査時(82%)から9.5%ポイント増加したこと、従業員数 300 人以下の事業者の導入率も46.9%となり、2016年の 26.3%から 20.6%ポイン ト上昇したことなどから、法改正の効果が確認されました。一方で体制整備の課題も見られています。例えば、従事者指定の義務については、「従事者指定の義務を知っているが、 担当者を指名していない」と回答した事業者が10.7%存在しています。また、内部通報制度を「導入している」と回答した事業者のうち、年間受付件数が「0件」、「1~5件」または「把握していない」と回答した事業者は65%にのぼっていることから、内部通報制度の実効性にも課題があることが分かりました。
こうした中、国際社会では、公益通報者保護への関心が一層高まっています。2019年に成立した「EU 通報者保護指令」や、同年に大阪サミットで採択された「効果的な公益通報者保護のためのハイレベル原則」では、各国に対して、公益通報者の保護を強化することを求めています。また、2024年5月、国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会は、訪日調査報告書で、公益通報者保護制度を強化すべきと指摘しました。
2024年5月から12月にかけて、有識者から構成される「公益通報者保護制度検討会」は、現状の課題について9回にわたり議論しました。その議論内容をふまえ、消費者庁は同年12月に、同検討会での報告書を発表。この報告書では、「事業者における体制整備の徹底と実効性の向上」「公益通報を阻害する要因への対処」「公益通報を理由とする不利益な取り扱いの抑止・救済」などの論点を軸に、今後見直すべきことに関して提言しました。





















