【解説】特別警報とは?種類や発表基準・警報との違いと警戒レベルとの関係・企業の事前対策
| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |
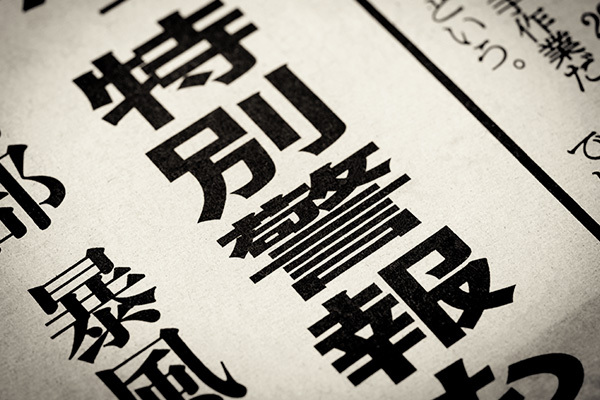
特別警報とは、甚大な災害が発生するおそれが非常に高まっている場合に気象庁が発表する防災気象情報です。「最大級の警戒」を呼びかけ、迅速な避難行動を促します。本記事では、特別警報の種類や発表基準、警報との違い、警戒レベルとの関係を整理し、企業の事前対策をわかりやすく解説します。
特別警報とは
特別警報とは、警報の発表後も大雨や暴風などが継続し、「警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合」(※1)に発表される防災気象情報です。気象庁が最上位の警戒を呼びかけるために発表します。
「最上位の警戒」とは、「数十年に一度のこれまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況」において、直ちに命を守るための行動が必要であることを示します。
特別警報が導入された背景には、2011年の東日本大震災における大津波や、平成23年台風12号がもたらした大雨などによる災害があります。当時、気象庁は警報を発表しましたが、災害の危険性が十分に伝わらず、避難や防災対応が遅れ、被害拡大につながったとされています。
この教訓を踏まえ、気象庁は気象業務法を改正し、甚大な災害の危険性をより明確に伝える制度として、2013年8月30日から「特別警報」の運用を開始しました。
特別警報が発表された場合は、既に何らかの災害が発生している可能性が極めて高い状況です。被害を防ぐためには、警報や注意報の段階から早めに避難行動を取ることが重要となります。
(※1)気象庁「特別警報について」
特別警報の種類と発表基準とは
気象庁が定める特別警報には、「気象などに関する特別警報」と「既存の警報を特別警報に位置づけるもの」の2種類があります。「既存の警報を特別警報に位置づけるもの」とは、地震や津波、噴火に関する一定レベル以上の警報を指します。
気象などに関する特別警報
気象などに関する特別警報には、大雨(土砂災害・浸水害)、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪の6種類があり、以下の図1の通り、雨、台風や温帯低気圧など、雪を要因とするものとして3つに大別されます。

図1:6種類の特別警報(大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪)の発表基準
特に、暴風、高潮、波浪、暴風雪に関する特別警報は、数十年に一度の強度の台風に起因するものだけでなく、それと同程度の猛烈に発達した温帯低気圧による暴風、高潮などが予想される場合にも発表されるため、注意が必要です。また、近年よく耳にするようになった雨を要因とする「大雨特別警報」は、数十年に一度の大雨や従来の避難指示レベルをはるかに超える異常な豪雨により、土砂災害や浸水害が発生する可能性が著しく高まった場合に発表されます。
大雨特別警報には、「土砂災害」と「浸水害」、または両方が付される場合があります。これらは、以下の基準で発表されます。
- 大雨特別警報(土砂災害):降雨により、土壌雨量指数(土壌中に溜まった水分量を示す指標)が気象庁の定めた基準を超えると予想されるとともに、今後も激しい雨が降り続くと予想される場合
- 大雨特別警報(浸水害):降雨により、表面雨量指数(短時間の強雨による浸水危険度の高まりを示す指標)または、流域雨量指数(河川の上流での降雨により、下流の対象地点の洪水危険度の高まりを示す指標)が気象庁の定めた基準を超えると予想されるとともに、今後も激しい雨が降り続くと予想される場合
- 大雨特別警報(土砂災害・浸水害):上記どちらにも該当する場合
なお、土砂災害に関する防災気象情報には、大雨特別警報(土砂災害)のほかに「土砂災害警戒情報」があります。土砂災害警戒情報とは、大雨警報(土砂災害)発表中に、土砂災害の危険度が非常に高まった場合に、都道府県と気象庁が共同で発表する防災気象情報です。これは、市町村長による避難指示の発令や、住民の自主避難の判断を支援するための情報であり、警戒レベル4に相当します。
これに対して「大雨特別警報」は、最大級の警戒を呼びかけるもので、自治体が緊急安全確保(警戒レベル5)を発令する判断材料にもなります。大雨特別警報の発表時点では、既に何らかの災害が発生している可能性が極めて高いため、土砂災害警戒情報が発表された段階で、速やかに避難行動を開始することが従業員の命を守ることにつながります。
さらに、近年の集中豪雨などによる自然災害の頻発化や激甚化を鑑み、2025年11月11日、「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これにより、気象庁は洪水の危険性をより速く確実に伝えるため、「洪水の特別警報」を新たに実施する旨を発表しました。
▼第1 気象業務法の一部改正
- 1 洪水の特別警報等の創設
- (1)気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、その旨を示して、洪水についての特別警報をしなければならないものとする。(第十三条の二第一項関係)
地震・津波・噴火に関する特別警報
地震、津波、噴火については、既存の警報を特別警報に位置づけるものとして、以下の図2に示す緊急地震速報、大津波警報、噴火警報の3つの情報があります。

図2:特別警報の種類と地震・津波・噴火の警報を特別警報に位置づけた図
「緊急地震速報」(震度6弱以上または長周期地震動階級4を予想したもの)、「大津波警報」、「噴火警報(居住地域)」は、危険度が非常に高いレベルを指すものです。大津波警報は、高いところで3mを超える津波が予想される場合、噴火警報(居住地域)は、居住地域に重大な被害をもたらす噴火が予想される場合に発表されます。
なお、これら3つの特別警報の発表には、「特別警報」の語句は用いられず、既存の名称で発表されます。例えば、「大津波警報」の発表は、津波に関する特別警報の発表を意味します。
特別警報と警戒レベルの関係とは
災害が発生、または危険が迫っている状況において、「行動を促す情報」と「取るべき行動」を直感的に把握することが重要です。内閣府が定めた「避難情報に関するガイドライン」では、これらを関連付けた「警戒レベル」を明記し、運用するよう求めています。
気象庁は、この「警戒レベル」に相当する防災気象情報と、住民が取るべき行動や市町村の対応をマッピングした行動指標を作成しています。警戒レベルは5段階に区分され、レベルごとの対応が示されています。

図3:防災気象情報に応じた警戒レベルと対応する行動
警戒レベル相当に該当する情報のうち、特別警報に当たるのは「大雨特別警報」と「高潮特別警報」です。図3の通り、大雨特別警報は、警戒レベル5相当、高潮特別警報は警戒レベル4相当に該当する情報とされています。
これら2つの特別警報を除いた、上述の気象などに関する特別警報のほか、既存の警報を特別警報に位置づける情報は、警戒レベル相当の情報に含まれないことがわかります。これは、警戒レベルが「自然災害のうち、人的被害が発生するもので、災害のおそれが段階的に発生する災害」を対象としているためです。
例えば、大津波警報は津波による災害発生の可能性が著しく高まり、予想される津波の最大波の高さが3mを超える場合に発表されます。津波は、突発的に発生する災害であり、災害の切迫度が段階的に上がる災害ではありません。市町村などから発表される避難指示を待たずに、津波注意報や警報が発表された段階で、一刻も早く避難することが求められます。複数の避難情報があると、住民の避難行動に混乱をきたすおそれがあるため、警戒レベルに関連づけはされていません。
特別警報に含まれる「暴風・波浪・暴風雪」といった気象現象に関しても、適時的確な避難情報の発令が困難であるため、警戒レベルの段階的な情報提供に馴染まないとされています。
そのため、警戒レベルに関連づかない場合の特別警報の発表においては、直ちに避難する、または安全を確保することと同義であることを念頭に、日々の訓練やシナリオ設計に取り入れることが重要です。
早期注意情報(警報級の可能性)とは
「早期注意情報(警報級の可能性)」は、警報級の気象現象が5日先までに発生すると予想された場合に、その可能性を知らせる防災気象情報です。「警報級の現象発生が差し迫る可能性」を数日前から通知することで、企業や自治体、住民が早期に災害への備えを行い、心構えを高めるなど、避難準備を支援することを目的としています。警戒レベル1相当に位置づけられており、災害への心構えを促す情報とされています。
早期注意情報は、特別警報と同様に、「大雨/大雪/暴風/暴風雪/波浪/高潮」の6つの気象現象を対象に発表されます。「翌日まで」、「2日先から5日先まで」の期間に、警報級の現象が起こる可能性が高い場合は[高]、可能性は高くないものの一定程度認められる場合は[中]と示されます。
なお、早期注意情報が発表されていない場合でも、天候の急変で警報や特別警報が出ることがあるため、企業は普段から警報発表の情報収集に努め、具体的な防災対応を迅速に実行できる体制構築が重要です。
特別警報が発表された過去の事例とは
過去、特別警報が発表された主な事例に、「令和元年東日本台風」や「令和2年7月豪雨」が挙げられます。これらは台風や梅雨前線に起因した大雨により、大雨特別警報が発表された事例です。
特別警報は、「数十年に一度のこれまでに経験したことがないような、重大な危険が差し迫った場合」に発表されるものですが、2024年は災害をもたらした気象事例が数回発生し、そのすべてで特別警報が発表されています。(※2)
(※2)気象庁「災害をもたらした気象事例(平成元年~本年)」
以下の表は、特別警報の運用開始以降に発表された代表的な事例一覧です。
【表1】特別警報が発表された過去の代表的な事例一覧
| 年月 | 特別警報 | 対象地域 | 気象事例 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月6日~12日 | 大雨特別警報 | 熊本県・鹿児島県 | 低気圧と前線による大雨 | 北日本から西日本にかけて広い範囲で大雨。総降水量600mm超の地点や、平年8月の月降水量の3倍以上の地点もあった |
| 2024年11月8日~10日 | 大雨特別警報 | 鹿児島県 | 令和6年11月8日からの大雨 | 奄美地方と沖縄本島地方では48時間降水量が600mm超。観測史上1位の値を更新 |
| 2024年8月27日~9月1日 | 高潮特別警報・波浪特別警報・暴風特別警報 | 鹿児島県 | 令和6年台風第10号による大雨、暴風及び突風 | 九州の複数の観測地点で8月の最大風速1位を更新 |
| 2020年7月3日~31日 | 大雨特別警報 | 九州地方・中部地方 | 令和2年7月豪雨(※a) | 球磨川、筑後川、飛騨川、江の川、最上川などの大河川が氾濫 |
| 2019年10月10日~13日 | 大雨特別警報 | 静岡県・新潟県・関東甲信地方・東北地方 | 令和元年東日本台風(※a) | 関東甲信地方、東北地方などで3、6、12、24時間降水量が観測史上1位の値を更新 |
| 2019年8月26日~8月29日 | 大雨特別警報 | 佐賀県、福岡県、長崎県 | 前線による大雨 | 福岡県と佐賀県の一部地域では3時間及び6時間降水量が観測史上1位の値を更新 |
| 2013年9月15日~16日 | 大雨特別警報 | 滋賀県・京都府・福井県 | 台風第18号による大雨 | 総降水量は、近畿地方で400mm超 |
(※a)顕著な災害を起こした自然現象の名称
気象庁「災害をもたらした気象事例(平成元年~本年)」と気象庁「過去の主な災害時の情報発表状況」を基にニュートン・コンサルティングが作成
表に示した通り、これまで発表された特別警報の多くは「大雨特別警報」となっています。加えて、近年では台風に限らず、警報の基準を大きく上回る記録的な大雨などにより、特別警報が発表されていることがわかります。
特に、令和2年7月豪雨は、2020年7月3日から7月31日までの長期にわたり、西日本から東日本の広範囲に甚大な被害が生じた事例です。
長期停滞した梅雨前線により、2020年7月4日から7日にかけて、九州地方では記録的な大雨となり、気象庁は7月4日未明から順次、熊本県をはじめとする九州地方の5県、続いて、岐阜県、長野県に大雨特別警報を発表しました。
この豪雨により、多くの河川が氾濫し、特に球磨川では堤防決壊による甚大な浸水被害が発生しました。球磨川流域にある人吉市の浸水面積は、約518ヘクタールで東京ドーム約111個分に及ぶなど、人的・物的被害が以下の通り甚大なものとなりました。(※3)
- 人的被害【死者・行方不明者】86名
- 人的被害【負傷者】77名
- 住家被害【半壊・一部損壊】8,007棟
- 住家被害【全壊】1,621棟
- 住家被害【浸水】6,971棟
(※3)内閣府「令和2年7月豪雨による被害状況等について(令和3年1月7日14:00現在)」
さらに、橋梁の破壊や流出により、交通インフラへの打撃も深刻なものとなったほか、広範囲で大気が不安定な状態となり、埼玉県では竜巻などの突風による被害も発生しました。
このように、特別警報が発表されるほどの気象状況では、人的・物的被害の発生や、交通インフラ・ライフラインにも影響が及ぶことを踏まえ、企業は平時にBCP(事業継続計画)の改善や従業員の安否確認体制の強化に取り組む必要があります。
特別警報を想定した企業の事前対策とは
特別警報は、「数十年に一度のこれまで経験したことがないような重大な危険が差し迫った異常な状況」で発表される防災気象情報の最上位にあたるものです。しかし、近年、特別警報の一つである「大雨特別警報」は年に2~3回の頻度で発表されており、まれなものではなくなりつつあります。
このような気象リスクの常態化に対応するため、企業は「特別警報が発表されたときにどう動くか」だけでなく、「警報や注意報の段階で、それぞれの情報に合わせてどう備えるか」を併せて検討することが肝心です。
特別警報が発表された際は、直ちに命を守る行動が求められるため、警報の段階で避難場所や避難所へ避難ができるよう、日ごろから安否確認体制を構築し、対策本部や他部署との連携・情報共有手段を複数確保しておきます。
その上で、以下のポイントを押さえることが重要です。
1.突発災害の視点を持つ
大雨による浸水や冠水、内水氾濫や外水氾濫は、従来、水害リスクとして、予報や予測があるため、被害が発生する前に対策を打つことができる進行型災害といわれていました。しかし、近年はその予測が難しい「線状降水帯」や「局地的大雨・短時間強雨」といった都市型水害を引き起こす可能性が高い水害リスクでもあるため、地震や火災と同じ「突発型災害」にもなりえるという捉え方に変えて、対策を講じる必要があります。
この場合、対策にかけられる時間は、数十分から数時間程度となるため、事前に準備を行います。
- 止水板や土のうの保管場所、設置方法、設置個所の共有
- 出退勤の調整やリモート・在宅ワークへの切り替えと基準の策定
- 「記録的短時間大雨情報」、「顕著な大雨に関する気象情報」や「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」といった情報の共有
上記のほか、「日本の年降水量は世界の約1.4倍、企業は水害リスクをどう捉えるべきか」や「企業が風水害に備えるために重要なポイントとは」では、水害リスクに備えるポイントを紹介しています。ぜひご活用ください。
2.災害シナリオ別に発災時と長期的な対策を講じる
地震や津波、噴火は、突発性が非常に高く、段階的な警戒が困難な災害です。発災した場合には、災害ごとに特性が異なるため、それぞれのシナリオに合わせた対策を講じるとともに、発災後は長期的な対応が求められることも踏まえておく必要があります。
- 津波の場合
-
- 本社や各拠点付近に、避難場所や津波避難ビルがあるか
- 避難が間に合わない場合の代替手段として、垂直避難が可能な施設が近隣にあるか
- 従業員を避難させるための経路を複数確保できるか
- 本社や生産・物流拠点が被災した場合を想定し、代替の調達先や生産拠点の協定を締結しているか
- 津波による浸水リスクの高い場所に拠点がないか
- ライフラインが途絶した場合の予備発電機確保や燃料の貯蔵をしているか
- 噴火の場合
-
- 本社や各拠点付近に、活火山があるか
- 噴火が企業活動にもたらす被害は何か
- 噴火警報、噴火速報、降灰予報、火山ガス予報などの噴火に関わる情報共有体制はあるか
- 降灰シミュレーションを実施し、影響度を把握しているか
- 噴火の場合の影響範囲を踏まえた上で代替拠点を確保しているか
特に、噴火は地震や津波よりも発生確率の低い災害ではありますが、ひとたび噴火すると、溶岩流や降灰、火砕流や火山ガス・火山泥流など、さまざまな火山現象をもたらします。「なぜ企業は噴火に備えなければいけないのか」では、火山噴火によるインフラ・経済活動への影響や企業が備えるべきポイントなどをまとめていますので、ぜひご覧ください。
このように、企業はそれぞれの災害の特性を理解し、想定される被害と業務への影響を具体的に想定した上で、平時から備えを構築することが望ましいといえます。
特別警報は、命を守るために最上級の警戒を呼びかける防災気象情報です。特別警報の発表の有無にかかわらず、企業や従業員は、特別警報・警報・注意報の段階的な変化を踏まえて、行動できる体制を整えておくことが重要です。さらに、定期的な訓練や手順を確認・検証することで、BCPの実効性を高め、結果として企業全体の防災力を継続的に向上させることが可能になります。従業員の安全と企業活動を止めないためにも、防災対策の見直しを習慣化することが求められます。






















