指定感染症
| 執筆者: | アソシエイトシニアコンサルタント 林 和志郎 |
| 改訂者: | ニュートン・コンサルティング 編集部 |
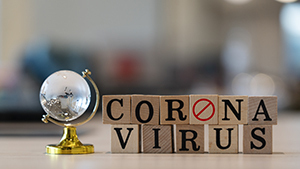
指定感染症とは感染症法(※)に基づく分類(カテゴリー)の一つです。感染性の疾病がここに分類される際には、感染症法に基づいて政令で定められます。最近では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が2020年1月から2021年2月まで、指定感染症に定められていました。指定感染症から外れた後は、別の分類である「新型インフルエンザ等感染症」に一類型として指定され、現在に至ります。このように、指定感染症とは未分類の感染性の疾病に対して講じる一時的な措置という側面があります。
※感染症法 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のこと
指定感染症の概要
「指定感染症」とは、感染症法の適用対象として認定されていないものの、適用対象にしなければ、その蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある疾病であり、早急な対応が必要な感染症であると政令指定したものをいいます。
ここで早急な対応が必要な感染症とは、認識されてから日が浅くまだ法律上の取り扱いが決まっていない(未分類である)ものの、とりあえず既知の影響力あるウイルス同様の国家的な対応が必要だと判断した感染症を言います。直近では2020年1月に日本国内で初の感染者を出した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が指定されていました。COVID-19は、2019年12月中旬に中国の武漢で初感染者が確認され、2020年1月に入って一気に広まりました。1月16日には日本国内で初の感染者が確認され、早急な対応をしなければ危険との判断から、1月28日に感染症法に基づく「指定感染症」として閣議決定されました(2月1日から施行)。
言い換えますと、「指定感染症」は一時的な指定措置であり、その措置は延長を含め最大2年間に限定されています。期限内に深い分析と検討を行い、その危険性がやはり大きいと判断されたものについては、危険性の大きさに応じて「1~5類」、「新型インフルエンザ等感染症」の類型に当てはめられることになります。また、必要に応じて新たな類型を作るのかまで検討されます。現在の分類は次のようになっています。
表1 感染症法に基づき規定された疾病
| 分類 | 疾病名の 規定方法 |
感染症法に基づき規定されている疾病 |
|---|---|---|
| 一類感染症 | 法律 | エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱等 |
| 二類感染症 | 法律 | 中東呼吸器症候群(MARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)等 |
| 三類感染症 | 法律 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等 |
| 四類感染症 | 法律 | デング熱、チクングニア熱、マラリア、ジカウイルス感染症、黄熱、鳥インフルエンザ(H5N1を除く) 等 |
| 五類感染症 | 法律 | インフルエンザ、性器クラミジア感染症、梅毒等 |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 法律 | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症 |
| 指定感染症 | 政令 | 該当なし |
| 新感染症 | 厚生労働大臣による公表 | 該当なし(発生時に決定) |
出典:厚生労働省「指定感染症及び検疫感染症について」※2022年10月時点
指定感染症に関する法的措置
感染症法では、感染症(1~5類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)に関して、国や地方公共団体、医療機関、医師等、国民が一丸となって感染拡大と蔓延を防ぐと定められています。具体的には次に示す取り組みがなされることになります。
表2 責務の主体とその対応内容
| 責務の主体 | 内容 |
|---|---|
| 国及び地方公共団体 |
|
| 医師等 |
|
| 国民 |
|
出典:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を基にニュートン・コンサルティングが作成
なお、この法令には罰則が伴います。この法律を遵守せず、周囲の人々に危険が及んだ場合(ウイルスを拡散させるような行為等)、懲役または罰金が課せられます。
企業としてすべきこと
ある感染症が「指定感染症」に認定されたとき、企業は具体的に何をしなければいけないのでしょうか。感染症法の第1章第4条で示されている「国民は、『感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意』を払うよう努めるとともに、『感染症の患者等の人権が損なわれることがないように』しなければならない」との定めを軸に考えるならば、企業に求められる活動はそれに寄与することです。すなわち、指定感染症が持つ意味とそれによって自社の対応方針がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)について従業員に伝えることです。
「指定感染症」への認定は「それだけ社会の脅威になる感染症が蔓延しつつある」ことのシグナルでもあるので、とりわけ下記事項を考慮して自社の対応方針を検討・決定することが望ましいでしょう。
- どういった特徴を持つ感染症なのか
- 最悪の事態とはどのような想定か
- 感染予防に対して会社としてどのような取り組みを推進するのか
どういった特徴を持つ感染症なのか
ただ恐怖を煽るだけでは、混乱を引き起こすだけで、それこそ人権を損ないかねません。適切に身を守るためには感染症の特徴を捉える必要があります。具体的には、感染力、致死率、感染経路、感染した際の症状、回復までの期間などの情報を集めます。COVID-19では、次のような特徴がありました。
【COVID-19の特徴】
- 誰もが感染するリスクを持つ
- 飛沫感染、エアロゾル感染
- 症状が出ない人もいる
- 発症までに1~14日間(多くは5日程度)、回復までに2週間かかる
- 高齢者の死亡率が高い
- 子供の感染経路は「親から子供」が多い
最悪の事態とはどのような想定か
こうした感染症が、個人や会社に対してもたらす最悪の事態は何であるのかについて、検討することが重要です。具体的には、従業員がどこで感染する可能性が高いのか、感染者が出た場合に最悪の事態としてどのような影響が個人・組織全体に出るのか、などといったことです。
感染予防に対して会社としてどのような取り組みを推進するのか

一般的な感染予防対策は「手洗い・うがい・マスク」です。それ以外にも通勤時の感染リスクを減らすため、自家用車・自転車通勤を許可したり、2日勤務して2日休むなどのシフト変更をしたりするなど、様々な対策があります。これらは企業の業務内容や施設・設備のレイアウトなどによって変わるため、専門家やメディアが推奨している主な対策にとどまらず、自組織を観察して必要な対策を適宜考えることが重要になります。併せて、指定感染症については、受診・入院できる病院は限られるため、特定感染症指定医療機関を従業員に会社からアナウンスするなどの工夫ができるでしょう。






















